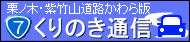来て!見て!にいこく広場

【にいこくひよっこ体験記】とは、新潟国道事務所(にいこく)の若手職員(係員)が仕事の中で体験したことをお知らせする「にいこく広場」です。
07 月 27 日更新(360)
- 良質なインフラ整備に貢献した優秀企業・技術者を表彰しました
-
7月25日(火)、新潟国道事務所において令和5年度 優良工事・委託業務等表彰式を行いました。
この表彰は、令和4年度に完成した工事及び委託業務等について、その施工又は成果が優秀で他の模範となる者、また優良工事を現場でサポートした下請負者を表彰するものです。
このたび、選定された工事5件、委託業務3件、建設技術者5名、下請負者3社、下請負者の技術者3名に表彰状が授与されました。
また、7月18日(火)に北陸地方整備局長表彰を受けた工事3件、委託業務1件、建設技術者3名、下請負者2社、下請負者の技術者2名の表彰状が披露されました。
受賞者を代表して東亜道路工業株式会社 北陸支店 執行役員 支店長 河西様より、
「本日の栄誉を糧に、ステークホルダーの皆様や地域、社会から強い信頼を得る企業を目指し、地域に密着した建設事業者として、更なる工事品質と安全管理向上をお誓いします。」との謝辞をいただきました。
関連URL:良質なインフラ整備に貢献した優秀企業・技術者を表彰します
07 月 25 日更新(359)
- 遊びにおいでよ!「道路ふれあいコーナー」へ!!
-
4年ぶりだよ「道路ふれあいコーナー」!
新潟まつり「お祭り広場」内で開催するよ!!
8月6日(日)は、ふるまちモール7に集合!!!
小型除雪車に乗って、暑い中除雪作業を想像してちょっぴりひんやりしたり、新潟市のシンボル萬代橋についてパネルや映像を見て身近に感じてみたりしませんか?
この他にクイズもあり、お子さまだけでなく大人も楽しめるイベントを用意して、スタッフ一同、首を長くしてお待ちしています。
詳しくは、チラシを見てね!
関連URL:2023年道路ふれあいコーナーチラシ
07 月 11 日更新(358)
- 東新潟中学校の2年生が「職場体験」でにいこくにやってきました。
-
7月5日(水)、6日(火)の2日間、東新潟中学校2年生が「職場体験」でにいこくに訪れ、にいこくの仕事を、座学や現場見学をとおして学び・体験していただきました!
まずはじめに、にいこくの仕事やITSコックピットについて、クイズに挑戦してもらいながら学んだのち、現場見学へ行きました。
1つ目の現場は、栗ノ木道路・紫竹山道路です。新潟維持出張所の屋上から全体を見渡し、栗ノ木道路・紫竹山道路の完成形をイメージしてもらいました。建設中の橋脚を見た生徒は、「橋脚はどのように作られますか?」と質問し、橋脚の作り方を学んでいました。
続いては村上市に移動し、朝日温海道路2号トンネルの工事現場を見学。工事中のトンネルの中を歩きながら、トンネルを作る機械や発破掘削で出た岩盤のかけら等を興味深そうに眺めていました。
事務所に戻った後は、24時間体制で道路の監視や情報の提供を行い、災害時には職員が集まり、情報収集や復旧等の災害対応を行う「ITSコックピット」を見学してもらいました。コックピット内の設備の説明や、にいこく管理区間に設置されたCCTV(道路監視用カメラ)を実際に操作してみて、道路の異常にいち早く気づける管理体制を体感していただけたと思います。
最後は、事前に考えてきてくれた質問や、当日お話を聞いたり、工事現場をみたりして疑問に思ったことなどをたくさん質問してもらい、新潟国道事務所が皆さんの生活を支えており、働くやりがいがあることをお伝えしました。
将来なりたい職業がある!という生徒も、今はまだ決めてない・・・という生徒もいましたが、この日の経験が将来やりたいことを考える上での材料になれば嬉しいです。
07 月 11 日更新(357)
- 「にいがた2km 未来を語るシンポジウム」を開催しました。
-
7月2日(日)、新潟市民プラザにて「にいがた2km 未来を語るシンポジウム」を開催しました。
国と新潟市では連携してまちづくりに取り組んでおり、昨年度の3月には学生や地域で活躍する社会人のみなさんと共に「にいがた2km 未来トークワークショップ」を行いました。今回のシンポジウムは、ワークショップでのアイデアをご紹介いただくなど、未来の新潟市のために今どんな種が蒔けるのかをさまざまな視点で語り合いました。
始めにLIFULL HOME’S 島原万丈氏による基調講演が行われました。
島原氏は「なんかこの街いいよね」という、感覚的だったものを数値化して都市の魅力を測れないか検討し、経験を「動詞」として評価する手法、「官能都市」調査(センシュアス・シティ・ランキング)を開発された方です。講演では、新潟市の今のランキングは134都市中38位であるとし、他都市と比較するとクルマ社会的な要素が高いと紹介しました。ランキング上位の都市では指標のうち「歩ける」「街を感じる」という要素が強く、歩かなくなると街の活気を感じなくなる傾向にあるため、新潟市でもぜひ「ウォーカブルなまちづくり」を進めてほしいとのアドバイスをいただきました。
続いて行われたパネルディスカッションでは、ワークショップに参加していただいたメンバーが登壇し、当日お越しいただいた約260人を前に、西堀ローサや万代クロッシング、水辺空間の活用、にいがた2km周辺の緑地化、移動手段の拡充など、それぞれが考える新潟のまちづくりのアイデアや未来のにいがた2kmへの期待をお話いただきました。
シンポジウムの締めくくりとして、中原新潟市長と内藤北陸地方整備局長によるトークセッションが行われ、これからのにいがた2kmを盛り上げるアイデアを発表していただいたパネリストへの感謝を伝えたのち、にいがた2kmの未来についての想いや現状の取り組み、そして今後の展望を語りました。
新潟国道事務所では、都心軸に集中する交通の転換を図り、まちづくりを支援するため、万代島ルート線の整備等を推進するとともに、新潟市と協力し、やすらぎ堤や万代テラスとのつながりなど面的な広がりを意識し、周辺の公共空間も含めた賑わい空間の創出に向け、取り組んでいきます。
関連URL:「にいがた2km 未来を語るシンポジウム」を開催!
- バックナンバー(PDF)
-
- 第125号(2023年08月号)
- 第124号(2023年07月号)
- 第123号(2023年06月号)
- 第122号(2023年05月号)
- 第121号(2023年04月号)
- 第120号(2023年03月号)
- 第119号(2023年02月号)
- 第118号(2022年11月号)
- 第117号(2022年10月号)
- 第116号(2022年08月号)
- 第115号(2022年06月号)
- 第114号(2022年04月号)
- 第113号(2022年03月号)
- 第112号(2022年02月号)
- 第111号(2022年01月号)
- 第110号(2021年11月号)
- 第109号(2021年10月号)
- 第108号(2021年09月号)
- 第107号(2021年04月号)
- 第106号(2020年10月号)
- 第105号(2020年09月号)
- 第104号(2020年08月号)
- 第103号(2020年06月号)
- 第102号(2020年04月号)
- 第101号(2020年03月号)
- 第100号(2020年02月号)
- 第99号(2019年11月号)
- 第98号(2019年10月号)
- 第97号(2019年09月号)
- 第96号(2019年08月号)
- 第95号(2019年07月号)
- 第94号(2019年06月号)
- 第93号(2019年04月号)
- 第92号(2019年03月号)
- 第91号(2019年02月号)
- 第90号(2019年01月号)
- 第89号(2018年12月号)
- 第88号(2018年11月号)
- 第87号(2018年10月号)
- 第86号(2018年09月号)
- 第85号(2018年08月号)
- 第84号(2018年07月号)
- 第83号(2018年06月号)
- 第82号(2018年05月号)
- 第81号(2018年04月号)
- 第80号(2018年03月号)
- 第79号(2018年02月号)
- 第78号(2018年01月号)
- 第77号(2017年12月号)
- 第76号(2017年11月号)
- 第75号(2017年10月号)
- 第74号(2017年09月号)
- 第73号(2017年08月号)
- 第72号(2017年07月号)
- 第71号(2017年06月号)
- 第70号(2017年4月号)
- 第69号(2017年3月号)
- 第68号(2017年2月号)
- 第67号(2017年1月号)
- 第66号(2016年12月号)
- 第65号(2016年11月号)
- 第64号(2016年10月号)
- 第63号(2016年9月号)
- 第62号(2016年8月号)
- 第61号(2016年7月号)
- 第60号(2016年6月号)
- 第59号(2016年5月号)
- 第58号(2016年4月号)
- 第57号(2016年3月号)
- 第56号(2016年2月号)
- 第55号(2016年1月号)
- 第54号(2015年12月号)
- 第53号(2015年11月号)
- 第52号(2015年10月号)
- 第51号(2015年9月号)
- 第50号(2015年7月号)
- 第49号(2015年6月号)
- 第48号(2015年5月号)
- 第47号(2015年4月号)
- 第46号(2015年3月号)
- 第45号(2015年1月号)
- 第44号(2014年12月号)
- 第43号(2014年11月号)
- 第42号(2014年10月号)
- 第41号(2014年9月号)
- 第40号(2014年8月号)
- 第39号(2014年7月号)
- 第38号(2014年6月号)
- 第37号(2014年5月号)
- 第36号(2014年4月号)
- 第35号(2014年3月号)
- 第34号(2014年2月号)
- 第33号(2014年1月号)
- 第32号(2013年12月号)
- 第31号(2013年11月号)
- 第30号(2013年10月号)
- 第29号(2013年9月号)
- 第28号(2013年8月号)
- 第27号(2013年7月号)
- 第26号(2013年6月号)
- 第25号(2013年5月号)
- 第24号(2013年4月号)
- 第23号(2013年3月号)
- 第22号(2013年2月号)
- 第21号(2013年1月号)
- 第20号(2012年12月号)
- 第19号(2012年11月号)
- 第18号(2012年10月号)
- 第17号(2012年9月号)
- 第16号(2012年8月号)
- 第15号(2012年7月号)
- 第14号(2012年6月号)
- 第13号(2012年5月号)
- 第12号(2012年4月号)
- 第11号(2012年3月号)
- 第10号(2012年2月号)
- 第9号(2012年1月号)
- 第8号(2011年12月号)
- 第7号(2011年11月号)
- 第6号(2011年10月号)
- 第5号(2011年9月号)
- 第4号(2011年8月号)
- 第3号(2011年7月号)
- 第2号(2011年6月号)
- 創刊号(2011年5月号)