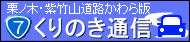来て!見て!にいこく広場

【にいこくひよっこ体験記】とは、新潟国道事務所(にいこく)の若手職員(係員)が仕事の中で体験したことをお知らせする「にいこく広場」です。
11 月 30 日更新(230)
- 建設リサイクル施設の現地見学を行いました
-
11月27日(月)、北陸建設副産物対策連絡協議会の新潟県下越分科会(にいこくが事務局)は、建設副産物の発生抑制、再利用および適正処理の推進を目的に、建設副産物のリサイクル施設への現地見学に行きました。
建設副産物とは、建設現場から発生したアスファルト廃材やコンクリート廃材、木材や残土などのことで、国をあげて取り組んでいる循環型社会の3R(「リデュース(発生抑制)」、「リサイクル(再生利用)」、「リユース(再利用)」)と同じような取り組みのひとつです。
新潟県下越分科会の会員から15名が参加し、新潟市秋葉区の(株)アドヴァンス新津工場と東区のエイ・エックス(株)山木戸工場を見学しました。
アドヴァンス新津工場では、ゴミ焼却炉から発生した溶融スラグ(ゴミ焼却場から出る燃えかすのことで、これまでは埋め立て処分していました。)を骨材として利用したコンクリート二次製品の生産を平成28年度から行っています。
コンクリート二次製品とは、工事現場でコンクリートを打設して施工するのでなく製品を工場で製作することにより現場での施工期間の短縮や品質の確保を目的とするもので、身近なところでは道路の雨水を排水する側溝があります。
溶融スラグ入りコンクリート二次製品使用の取り組みについて構成6者からなるにいがたエコ・コンクリート工業会の担当の方から説明を受け、活用スキームや溶融スラグの見本、製造過程や製品見本の見学を行いました。
エイ・エックス山木戸工場では、アスファルト廃材やコンクリート廃材を再資源化する施設で今年9月より稼働を始めた新しい施設です。建設現場から発生したアスファルト廃材やコンクリート廃材の処理方法や再生したアスファルト合材の製造過程、品質試験について担当の方から説明を受けました。
私たちが普段何気なく利用している道路や、目にしているコンクリートにも建設副産物が使われています。にいこくでは、限りある資源を有効活用できるよう、このような取り組みを進めていきます。
11 月 29 日更新(229)
- 見て触れて!〜児童が除雪について体験学習〜
-
11月27日(月)関川村立関川小学校1年生(36名)の皆さんが、「いろいろな働く車について比較する『自動車くらべ』」の授業で関川除雪ステーションを訪れ、除雪体験学習を行いました。
体験学習では、除雪機械のデモンストレーション、除雪ステーション内部の見学、除雪機械への乗車や道路に散布する凍結防止剤(塩)に触れたりしました。
前日まで降っていた雨は止み、少し肌寒い空の下でしたが、体験学習に参加した小学生は「除雪車がかっこよかった。」「とっても楽しかった。」と感想を話すなど、元気に飛び回りながら学んでいた姿が私たちにも活気を与えてくれました。
このような体験学習を通じて、地域の人々の暮らしを守る人がいることを学び、記憶に残しておいていただければと思います。
11 月 22 日更新(228)
- 知っていますか?朝日温海道路はどんな道路
-
朝日温海道路は、新潟県・山形県・秋田県の主要都市を結び青森県に至る延長約322km(新潟空港IC〜青森IC)の日本海沿岸東北自動車道(日沿道)のうち、新潟・山形県境の「朝日まほろばIC〜あつみ温泉IC」区間(延長約40.8km)の自動車専用道路です。
日沿道の一部分を形成する朝日温海道路が整備されると、新潟山形間が高速道路で結ばれ、災害に強い安定した輸送ルートが確保できます。
また、地域にとっては、時間短縮による救命率の向上や、地域の観光活性化につながるチャンスが生まれます。私も地域に住む一人として、常々地域の将来を考えていますが、朝日温海道路に携わる立場からも地域がさらに活性化するよう、地域の将来を考えていきたいと思います
今年9月に、朝日温海道路の起工式が行われて、現在1号トンネル工事に本格着手しています。朝日温海道路ホームページの工事進捗情報でも随時更新していきますので、どうぞご覧ください。
さてどんな道路かはここまでで紹介しましたが、余談で・・・道路をつくるための手順を知ってますか?以下で一般的な手順を紹介します。
まずは地域の方々への「全体計画説明会」から始まり、色々なお話を伺いつつ、測量、地質調査などを行います。
次に道路、橋梁、トンネルなどの設計です。同時に関係する地域の方々と道路の構造などについて話し合いをします。
さらに道路を作るための土地を買収します。その土地に遺跡があるかどうか確認する埋蔵文化財調査を行い、いよいよ工事にとりかかります。
最後に、道路が完成したら維持するための道路の管理へと移っていきます。
こうやって見ると私たちの立場からだけではなく、地域の方々や関係機関の立場からも考えてみることが大切だと感じました。
より良い道路をつくるために、どうぞご理解とご協力をお願い致します。
関連URL:朝日温海道路ホームページ「工事進捗情報」
11 月 17 日更新(227)
- 「おにぎりで、いこう!」国道おにぎりキャンペーンとコラボレーション!
-
11月12日(日)に新潟ふるさと村と道の駅あらいにて、新潟県が主催する「おにぎりで、いこう!」の国道おにぎりキャンペーンが行われました。
新潟県では、新潟米おにぎりキャンペーンを毎年実施しています。今年度はおにぎりを使った学生企画コンテストを行い、その中で「国道おにぎり」を最優秀賞として、発表しています。
なぜ、おにぎりと国道が・・・!?おにぎりを逆さにして、よく見ると、なんとなく国道の標識に似ていませんか?そこに着目した学生さんが応募して、その結果最優秀賞に輝いたとのことです。
キャンペーン当日は、200名に国道おにぎりを配布していました。具材は、それぞれの国道にある地域の特産品にちなんだ具でした。あっという間に品切れになったようです。
そのキャンペーンで、にいこくのパネル(白根バイパスと朝日温海道路)も一緒に展示してもらい、一緒にPRを行いました。
そろそろ雪の季節になりますが、晩秋のドライブにおにぎりを持って出かけてみるのも良いと思います。その時はその地域にある道の駅にもぜひお立ち寄りください。
11 月 14 日更新(226)
- 萬代橋が青色にライトアップされました!
-
11月14日は、「世界糖尿病デー」に制定されています。この日に合わせ、毎年著名な建築物などのブルーライトアップがされています。
新潟県では、新潟県糖尿病協会と新潟県糖尿病推進会議が連携し、ブルーライトアップの活動を行っています。昨年度は、新潟市中央区にあるNEXT21で行っていましたが、今年度は4年ぶりに萬代橋が青色にライトアップされています。11月12日(日)から11月19日(日)までです。
普段の色合いとは、違った雰囲気で、新潟市で行っているやすらぎ堤の「彩り蛍」とマッチしているようでした。
折角の機会ですので、もしよかったら一度ご覧になって見てください。ただ、雰囲気は良いのですが、とても寒いですので暖かい服装でお出かけください。マフラー、手袋があるとなお良しです。
11 月 09 日更新(223)
- 知ってますか?国が管理していない国道があるのです!
-
知っていますか?国道には、国が管理していない区間があるのです。
すべての国道は国が管理していると思われがちですが、実は「指定区間」という制度があって、それによって道路の管理者が変わります。指定区間の国道は「直轄国道」と言って、国土交通省が管理しますが、それ以外の国道は「補助国道」と言って都道府県や政令市が管理しています。ご存じでしたか?
今定められている道路に関する法律の一つに「道路法」というものがあります。当初、全ての国道は都道府県によって管理することとなっていました(これも意外なことです。知っていましたか?)。その後、広域的な交通を担う道路については路線ごとに一貫した管理を行う必要があったため、昭和33年から指定する区間については国で管理するようになりました。
指定区間(直轄国道)には、交通量の多い区間で、改良や舗装を概ね完了した区間が指定されています。
にいこくでは、指定区間の5路線239.2kmを管理しています。いずれも広域交通を担う道路で、大型車の通行も多い重要な道路です。
なお、高速道路や国道で道路の穴ぼこ、路肩の崩壊などの道路損傷、落下物や路面の汚れなど道路の異状を発見された際は、道路緊急ダイヤル(#9910)へご連絡ください。
11 月 08 日更新(222)
- 木山小学校の児童が除雪出動式に参加しました!
-
11月1日(水)新潟市西区新通にある新潟西除雪ステーションで、近くにある木山小学校の4年生児童も参加して、にいこくの除雪出動式が行われました。
除雪出動式では、代表で一人の児童が、「除雪作業をしてくれて、ありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします」と応援メッセージを除雪業者に贈りました。その後、除雪開始の意味を持つコールドキーが児童から除雪業者に手渡されました。
除雪出動式が終わった後、児童達は、「除雪体験学習会」として、にいこく職員から新潟の除雪の話を聞きいたり、実際に除雪車に乗ったりしました。体験した児童達の感想は、「色々な除雪車があってびっくりした」や「除雪車には操作ボタンがいっぱいあった」でした。やはり除雪の話よりは、除雪車のほうに興味があったようです。
さて、新潟では、これから本格的な雪のシーズンを迎えます。皆さんも早めの冬の対策をしていただきますようお願いいたします。
- バックナンバー(PDF)
-
- 第123号(2023年06月号)
- 第122号(2023年05月号)
- 第121号(2023年04月号)
- 第120号(2023年03月号)
- 第119号(2023年02月号)
- 第118号(2022年11月号)
- 第117号(2022年10月号)
- 第116号(2022年08月号)
- 第115号(2022年06月号)
- 第114号(2022年04月号)
- 第113号(2022年03月号)
- 第112号(2022年02月号)
- 第111号(2022年01月号)
- 第110号(2021年11月号)
- 第109号(2021年10月号)
- 第108号(2021年09月号)
- 第107号(2021年04月号)
- 第106号(2020年10月号)
- 第105号(2020年09月号)
- 第104号(2020年08月号)
- 第103号(2020年06月号)
- 第102号(2020年04月号)
- 第101号(2020年03月号)
- 第100号(2020年02月号)
- 第99号(2019年11月号)
- 第98号(2019年10月号)
- 第97号(2019年09月号)
- 第96号(2019年08月号)
- 第95号(2019年07月号)
- 第94号(2019年06月号)
- 第93号(2019年04月号)
- 第92号(2019年03月号)
- 第91号(2019年02月号)
- 第90号(2019年01月号)
- 第89号(2018年12月号)
- 第88号(2018年11月号)
- 第87号(2018年10月号)
- 第86号(2018年09月号)
- 第85号(2018年08月号)
- 第84号(2018年07月号)
- 第83号(2018年06月号)
- 第82号(2018年05月号)
- 第81号(2018年04月号)
- 第80号(2018年03月号)
- 第79号(2018年02月号)
- 第78号(2018年01月号)
- 第77号(2017年12月号)
- 第76号(2017年11月号)
- 第75号(2017年10月号)
- 第74号(2017年09月号)
- 第73号(2017年08月号)
- 第72号(2017年07月号)
- 第71号(2017年06月号)
- 第70号(2017年4月号)
- 第69号(2017年3月号)
- 第68号(2017年2月号)
- 第67号(2017年1月号)
- 第66号(2016年12月号)
- 第65号(2016年11月号)
- 第64号(2016年10月号)
- 第63号(2016年9月号)
- 第62号(2016年8月号)
- 第61号(2016年7月号)
- 第60号(2016年6月号)
- 第59号(2016年5月号)
- 第58号(2016年4月号)
- 第57号(2016年3月号)
- 第56号(2016年2月号)
- 第55号(2016年1月号)
- 第54号(2015年12月号)
- 第53号(2015年11月号)
- 第52号(2015年10月号)
- 第51号(2015年9月号)
- 第50号(2015年7月号)
- 第49号(2015年6月号)
- 第48号(2015年5月号)
- 第47号(2015年4月号)
- 第46号(2015年3月号)
- 第45号(2015年1月号)
- 第44号(2014年12月号)
- 第43号(2014年11月号)
- 第42号(2014年10月号)
- 第41号(2014年9月号)
- 第40号(2014年8月号)
- 第39号(2014年7月号)
- 第38号(2014年6月号)
- 第37号(2014年5月号)
- 第36号(2014年4月号)
- 第35号(2014年3月号)
- 第34号(2014年2月号)
- 第33号(2014年1月号)
- 第32号(2013年12月号)
- 第31号(2013年11月号)
- 第30号(2013年10月号)
- 第29号(2013年9月号)
- 第28号(2013年8月号)
- 第27号(2013年7月号)
- 第26号(2013年6月号)
- 第25号(2013年5月号)
- 第24号(2013年4月号)
- 第23号(2013年3月号)
- 第22号(2013年2月号)
- 第21号(2013年1月号)
- 第20号(2012年12月号)
- 第19号(2012年11月号)
- 第18号(2012年10月号)
- 第17号(2012年9月号)
- 第16号(2012年8月号)
- 第15号(2012年7月号)
- 第14号(2012年6月号)
- 第13号(2012年5月号)
- 第12号(2012年4月号)
- 第11号(2012年3月号)
- 第10号(2012年2月号)
- 第9号(2012年1月号)
- 第8号(2011年12月号)
- 第7号(2011年11月号)
- 第6号(2011年10月号)
- 第5号(2011年9月号)
- 第4号(2011年8月号)
- 第3号(2011年7月号)
- 第2号(2011年6月号)
- 創刊号(2011年5月号)