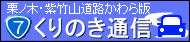来て!見て!にいこく広場

【にいこくひよっこ体験記】とは、新潟国道事務所(にいこく)の若手職員(係員)が仕事の中で体験したことをお知らせする「にいこく広場」です。
11 月 21 日更新(309)
- 木山小学校4年生が新潟西除雪ステーションで除雪について学びました
-
11月6日(水)、新潟市立木山小学校4年生8名が、新潟西除雪ステーションで、除雪について学びました。
当日は早朝まで冷たい雨が降っており、予定通りの内容で開催できるか不安でしたが、児童のみなさんがステーションに到着する頃には天候も回復していました。
最初のデモンストレーションでは、職員が、4台の除雪機械(除雪トラック、グレーダ、ロータリー除雪車、凍結防止剤散布車)の動きやそれぞれの役割について説明を行いました。児童たちの興味深く観察している姿、ノートに除雪車の絵を熱心に描いている姿を見ることができました。
次に除雪ステーションの施設内を見学してもらいました。執務室内からすぐ近くのCCTVカメラ(道路監視用カメラ)の位置や映像、食堂や仮眠室などを見てもらい、冬の間、除雪作業をする方々が24時間体制で除雪作業にあたる場所であることを知ってもらいました。その後、薬剤庫へ移動し、散布する凍結防止剤(塩化ナトリウム等)はどのようなものなのか触って確かめ、凍結防止剤をクレーンと架台を利用して薬剤散布車に積み込むしくみについても学んでもらいました。
最後に除雪機械に搭乗してもらいました。児童のみなさんが、運転席に座ってオペレータの方の説明を興味深く聞いていた姿や、ハンドルや操作レバーを握ってオペレータになったつもりで体験していた姿がとても印象的でした。
アナウンサーや新聞記者の方々からインタビューを求められるシーンもあり、児童のみなさんはこの総合学習を通じて、貴重な体験ができたのではないかと思います。
寒い中での体験学習となりましたが、皆さん、本当にお疲れ様でした。
11 月 18 日更新(308)
- 白根除雪ステーションで除雪出動式を行いました
-
11月5日(火)に、今年3月に全線開通した国道8号白根バイパスに隣接した白根除雪ステーションで除雪出動式を開催しました。
出動式には、除雪作業をする方々、にいこく職員、地元の新潟市立茨曽根小学校4年生5名の児童、総勢約60名で除雪期間中の安全を誓いました。
式典では、児童1人1人から温かい激励メッセージと共に、除雪開始の意味を持つゴールドキー、そして手作りのお守りが4出張所の除雪作業を行う代表者に手渡されました。
今冬の除雪を担う代表者からは、「長年培ってきた経験を生かし、ライフラインである直轄国道を守っていく」との決意表明がありました。
出動式後、茨曽根小学校の児童には、体験学習会に参加してもらいました。除雪機械のデモンストレーションで機械の名称、その動きと役割について学んでもらいました。また、除雪機械の搭乗体験で除雪作業をするオペレータの方の説明を興味深く聞いていました。施設内の見学では、道路に散布する凍結防止剤(塩化ナトリウム等)がどのようなものか見て触ってもらい、執務室や待機場所となる各部屋にも入ってもらいました。
みんな楽しく熱心に学習されていて本当にお疲れ様でした!
準備した一人として、お守りと最後に児童の皆さんから暖かいお礼の言葉を頂き、大変嬉しく思うとともに、この思いを忘れず今冬の道路管理の業務にあたっていきたいと思いました。
にいこくは、全国屈指の交通量を担う新潟市街地のバイパスから国道49号・113号の県境山間部まで、平地から山地に至る約232キロメートルの除雪区間を担当しています。にいこくでは、冬の国道の道路交通を守るため、今冬も重要な道路を管理しているという使命感を持ち、除雪にあたります。
ドライバーの皆様には冬用タイヤの早期装着やタイヤチェーンの携行をお願いするとともに、除雪作業へのご理解とご協力をお願い致します。
11 月 14 日更新(307)
- 「第31回 日本海夕陽ラインシンポジウムin村上」開催!
-
「日本海夕陽ラインシンポジウム」は、新潟市から青森市を繋ぐ全長約322kmの日本海沿岸東北自動車道(以下、日沿道)の早期開通を願って、沿線の青年会議所が組織した「日本海夕陽ラインネットワーク協議会」により昭和62年から開催されているシンポジウムです。
令和元年10月26日(土)、村上市において、第31回となるシンポジウムが、基調講演と日沿道のトンネル工事や埋蔵文化財調査の現場見学報告会の2部構成で開催されました。
基調講演では、村上市において長年まちづくりプロジェクトに取り組まれている、株式会社きっかわ専務取締役吉川美貴氏から、日沿道の開通を地域活性化に活かす方法に関するお話がありました。
現場見学報告会では、日沿道の工事現場に近接している、村上市立朝日さくら小学校4年生から、見学して学んだことや感じたことの報告がありました。
にいこくでは、日沿道が開通する頃に運転するようになる朝日さくら小学校4年生を対象に、現場見学会の全体の行程を組み、児童のみなさんに現場見学会で楽しく事業を学んでもらえるよう協力させていただきました。また、私から児童に日沿道の概要や開通による効果、完成するまでの流れについて説明を行ったところ、今回の報告会において児童から、私の説明についても報告されており、しっかり学んでくれたことをうれしく思いました。
また、会場展示パネルを作成し、来場者の方々に日沿道の概要や整備効果、村上市の魅力をお伝えしました。今回のパネル展示を通じて、日沿道開通を見越した地域活動が行われていることを知り、日沿道の開通効果を有効活用するためには地域の取組が重要であることをアピールできました。
シンポジウム全体を通じて、日沿道の早期開通が強く望まれていることや、日沿道開通前から開通による効果を地域で有効活用するための検討がされていることを改めて知り、自らの仕事を誇らしく思うと共に、しっかりと事業を進めていくことが重要であると感じました。
11 月 11 日更新(306)
- 特殊車両取締りを実施しました
-
10月29日(火)巻除雪ステーションにおいて、特殊車両取締りを実施しました。
特殊車両とは、車両の構造や輸送する貨物が特殊である車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかが一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等を通行する際に総重量、高さのいずれかの制限値を超えたりする車両のことで、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)
過積載や無許可の大型車両などの走行は道路の損傷や重大事故につながるおそれがあるため、事故を未然に防ぎ、規則を周知・理解していただくことを目的に取締りを実施しています。
取締りには、新潟国道事務所と黒埼維持出張所の職員約30名が参加したほか、新潟県警察西蒲警察署にもご協力いただきました。
取締りに初めて参加する若手職員が多い中、先輩職員に取締りの基本や計測機器の操作方法などを教えていただきながら、真剣に取り組みました。現地では、取締りに協力いただけるよう真摯に対応している先輩方の姿を見ることで、若手職員としては、重量や寸法の計測方法だけでなく、対人面でも学ぶところが多かったです。
昨今、特殊車両に限らず、交通事故や道路の維持管理等に関する問題は社会全体から注目されています。今後も道路行政を担当する国土交通省の職員であるという自覚を持って、今回の取締まりへの参加をきっかけとして気持ちを新たに業務に取り組みたいと思います。
- バックナンバー(PDF)
-
- 第123号(2023年06月号)
- 第122号(2023年05月号)
- 第121号(2023年04月号)
- 第120号(2023年03月号)
- 第119号(2023年02月号)
- 第118号(2022年11月号)
- 第117号(2022年10月号)
- 第116号(2022年08月号)
- 第115号(2022年06月号)
- 第114号(2022年04月号)
- 第113号(2022年03月号)
- 第112号(2022年02月号)
- 第111号(2022年01月号)
- 第110号(2021年11月号)
- 第109号(2021年10月号)
- 第108号(2021年09月号)
- 第107号(2021年04月号)
- 第106号(2020年10月号)
- 第105号(2020年09月号)
- 第104号(2020年08月号)
- 第103号(2020年06月号)
- 第102号(2020年04月号)
- 第101号(2020年03月号)
- 第100号(2020年02月号)
- 第99号(2019年11月号)
- 第98号(2019年10月号)
- 第97号(2019年09月号)
- 第96号(2019年08月号)
- 第95号(2019年07月号)
- 第94号(2019年06月号)
- 第93号(2019年04月号)
- 第92号(2019年03月号)
- 第91号(2019年02月号)
- 第90号(2019年01月号)
- 第89号(2018年12月号)
- 第88号(2018年11月号)
- 第87号(2018年10月号)
- 第86号(2018年09月号)
- 第85号(2018年08月号)
- 第84号(2018年07月号)
- 第83号(2018年06月号)
- 第82号(2018年05月号)
- 第81号(2018年04月号)
- 第80号(2018年03月号)
- 第79号(2018年02月号)
- 第78号(2018年01月号)
- 第77号(2017年12月号)
- 第76号(2017年11月号)
- 第75号(2017年10月号)
- 第74号(2017年09月号)
- 第73号(2017年08月号)
- 第72号(2017年07月号)
- 第71号(2017年06月号)
- 第70号(2017年4月号)
- 第69号(2017年3月号)
- 第68号(2017年2月号)
- 第67号(2017年1月号)
- 第66号(2016年12月号)
- 第65号(2016年11月号)
- 第64号(2016年10月号)
- 第63号(2016年9月号)
- 第62号(2016年8月号)
- 第61号(2016年7月号)
- 第60号(2016年6月号)
- 第59号(2016年5月号)
- 第58号(2016年4月号)
- 第57号(2016年3月号)
- 第56号(2016年2月号)
- 第55号(2016年1月号)
- 第54号(2015年12月号)
- 第53号(2015年11月号)
- 第52号(2015年10月号)
- 第51号(2015年9月号)
- 第50号(2015年7月号)
- 第49号(2015年6月号)
- 第48号(2015年5月号)
- 第47号(2015年4月号)
- 第46号(2015年3月号)
- 第45号(2015年1月号)
- 第44号(2014年12月号)
- 第43号(2014年11月号)
- 第42号(2014年10月号)
- 第41号(2014年9月号)
- 第40号(2014年8月号)
- 第39号(2014年7月号)
- 第38号(2014年6月号)
- 第37号(2014年5月号)
- 第36号(2014年4月号)
- 第35号(2014年3月号)
- 第34号(2014年2月号)
- 第33号(2014年1月号)
- 第32号(2013年12月号)
- 第31号(2013年11月号)
- 第30号(2013年10月号)
- 第29号(2013年9月号)
- 第28号(2013年8月号)
- 第27号(2013年7月号)
- 第26号(2013年6月号)
- 第25号(2013年5月号)
- 第24号(2013年4月号)
- 第23号(2013年3月号)
- 第22号(2013年2月号)
- 第21号(2013年1月号)
- 第20号(2012年12月号)
- 第19号(2012年11月号)
- 第18号(2012年10月号)
- 第17号(2012年9月号)
- 第16号(2012年8月号)
- 第15号(2012年7月号)
- 第14号(2012年6月号)
- 第13号(2012年5月号)
- 第12号(2012年4月号)
- 第11号(2012年3月号)
- 第10号(2012年2月号)
- 第9号(2012年1月号)
- 第8号(2011年12月号)
- 第7号(2011年11月号)
- 第6号(2011年10月号)
- 第5号(2011年9月号)
- 第4号(2011年8月号)
- 第3号(2011年7月号)
- 第2号(2011年6月号)
- 創刊号(2011年5月号)