関屋分水路:越後平野は人がつくった川ばかり
人工河川は、関屋分水路だけではありません。
大昔、越後平野は海でした。そこに、川が大量の土砂を運び、海の底にたまった土砂を波や冬の季節風が陸に向かって吹き上げ、長い年月をかけ越後平野はつくられてきました。
海岸部に発達した砂丘によって、越後平野を流れるたくさんの川は海への出口をふさがれ、氾らんをくり返し、人々を苦しめます。
そこで、人々は洪水の被害が少なくなるよう、また広い農地を求めて、多くの川(放水路)を掘ってきたのです。越後平野は、まさに「放水路銀座」です。
越後平野の潟と放流路
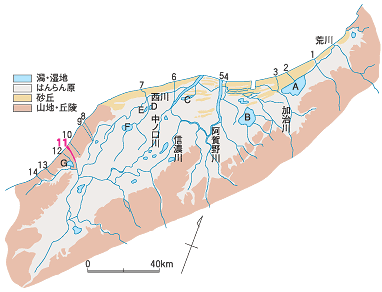
放流路通水年
- 胎内川放流路(1888)
- 落堀川(1733)
- 加治川放水路(1913)
- 新井郷川放水路(1934)
- 松ヶ崎放水路(阿賀野川)(1731)
- 関屋分水路(1972)
- 新川放水路(1820)
- 樋曽山隧道(1939)
- 新樋曽山隧道(1968)
- 国上隧道(1991)
- 大河津分水路(1922)
- 円上寺隧道(1920)
- 郷本川(1873)
- 落水川(1920)
干拓年
- 紫雲寺潟(1733)
- 福島潟(江戸時代以降)
- 鳥屋野潟(江戸時代以降)
- 大潟(1820〜1950)
- 田潟(1820〜1950)
- 鎧潟(1820〜1966)
- 円上寺潟(1883)
