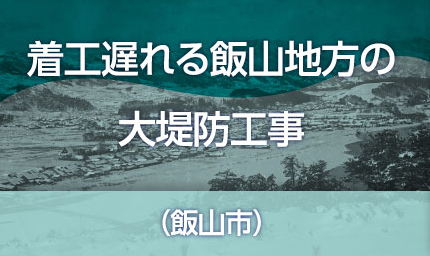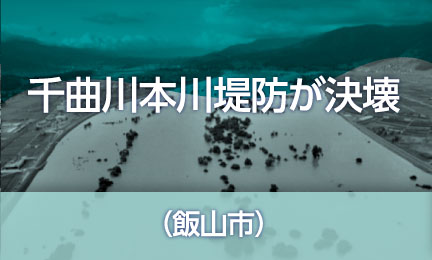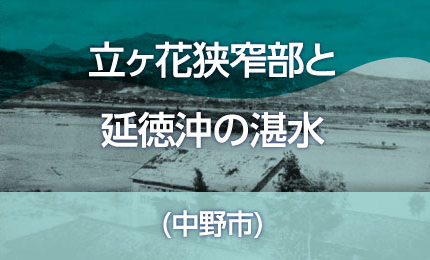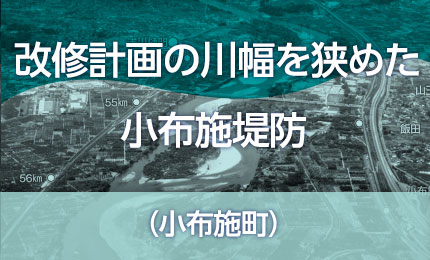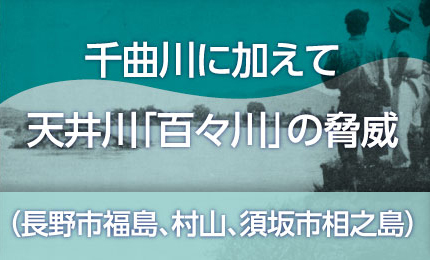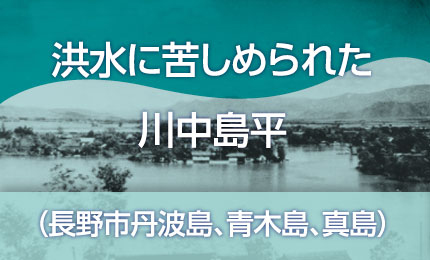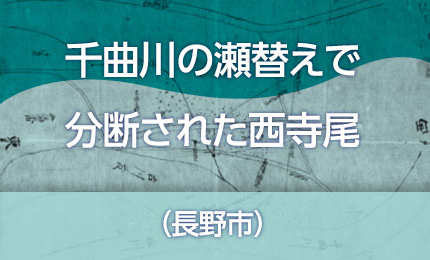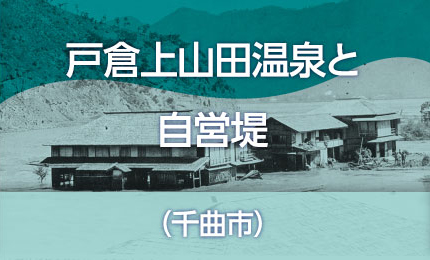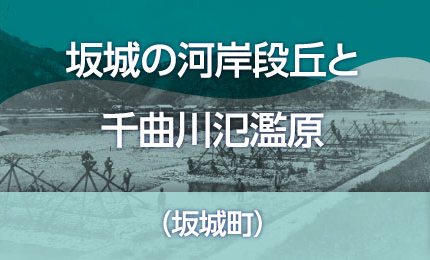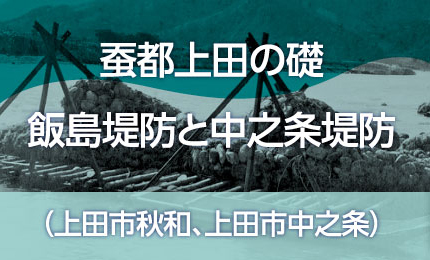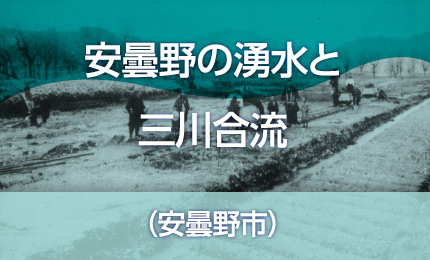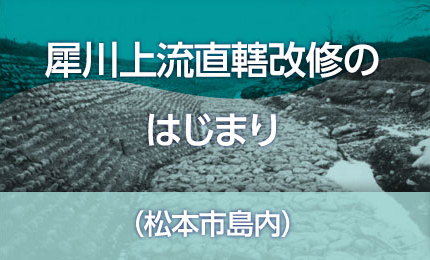安曇野の湧水と三川合流(安曇野市)
湧水が育む安曇野
松本平で最も標高が低く、3000m級の北アルプスからまっすぐ流れ下る高瀬川や穂高川と、松本平を北上する犀川が合流する安曇野。
豊富で清冽な湧水があり、また、小石や砂などの砂利で構成される河床は、かつては鮭の産卵適地だった。そうした環境を活かし日本を代表するワサビ農園として発展した。
ワサビ栽培は、梨畑として開墾され、その病害虫対策としてつくられた排水路に、自家用として栽培されてきたワサビを販売用として出荷したのが始まりといわれている。明治44年に中央線が開通し東京・名古屋へ方面へ出荷できるようになったこと、関東大震災で伊豆、静岡の産地が大被害を受けたことがきっかけで現在の基礎ができたといわれる。
複雑に合流する三川
高瀬川、穂高川は北アルプスから土砂を伴って急こう配で洪水が流れ下り、安曇野で扇状地を形成し犀川と合流する。いわゆる三川合流であるが、それぞれ河床高が著しく異なり互いにぶつかり合うように合流するため、広大な氾濫原となって洪水の流れも安定しなかった。このため安曇野地域と下流の明科地区では、明治・大正時代には毎年、昭和になっても洪水が頻発した。
水理模型実験
安全に三川を合流させるため、昭和38年から旧建設省土木研究所で模型実験による全体計画の策定が行われた。堤防の引堤や導流堤、水制工などからなる計画で、昭和43年度から工事に着手し、同53年に完了した。高瀬川上流には昭和61年大町ダムが完成している。