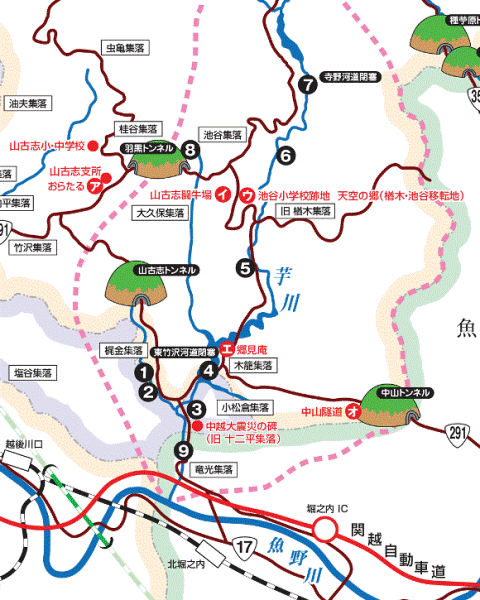地域がまるごと「自然とくらしの博物館」
芋川流域に位置する山古志地域周辺では、人々が自然とともに生きる暮らしの中で棚田の風景、錦鯉、重要無形文化財の闘牛(牛の角突き) などを育んできました。
新潟県中越地震で地盤が突き崩され、芋川流域では大きな土砂ダム(河道閉塞、天然ダムともいう)が生じて集落水没や決壊洪水の危機等を 経験しましたが、多くの人の想いと土木技術によって乗り越えてきました。今も国道等からいろいろな砂防施設を間近に見ることができます。
当地では、独特の歴史文化、風景、災害体験、砂防施設、地域の復興過程等、すべてが来訪者や新しい世代にとって学びの対象になります。
芋川流域の土砂災害被害
2004年(平成16年)10月23日に発生した新潟県中越地震によって、中越地方の中山間地では同時多発的に約1,550箇所で地すべりや崩壊が おこりました。旧山古志村では点在する集落が孤立するなどし、全村避難を余儀なくされました。
芋川流域では、地震直後に地すべりによる大小の土砂ダムがいくつも形成されて、上流側の住宅が水没しました。また、土砂ダム決壊による 大土石流が下流を襲う危険が迫りました。
土砂災害に立ち向かう力が結集
この窮地は、全国から技術と機材を結集した砂防事業によって回避することができ、地域は新たな歩みを始めることとなりました。 早期の復旧を果たすことができた大きな理由として、国、県、市、住民及び研究者が連携して取り組んできたことが挙げられます。
この経験はその後発生した新潟県中越沖地震や岩手宮城内陸地震、中国四川大地震など、国内外で発生する大規模な土砂災害に活かされること となりました。
土砂災害の被害を受けやすい中山間地
全国には長い時間をかけて人と自然と共存してきた中山間地が数多くあります。これらの地域は、ひとたび大きな土砂災害が発生すると 集落自体が消滅する可能性も否めません。また、人が住まなくなることで山が荒れ、新たな土砂流出の発生源となることが考えられます。
日本の原風景ともいえる美しい棚田の風景や牛の角突きなど独特の文化を育み、被災後も住民がふるさとへの想いをつないできた山古志地域 でも、この先、地震や大雨による土砂災害が起こらないとは限りません。
3つのコンセプト
そこで、新潟県中越地震の教訓、短期で復旧させた砂防技術、その過程で注がれた人の想いや連携の力などを継承するための「芋川砂防フィールドミュージアム」のコンセプトを掲げました。
- 地域防災力向上
- 地域の絆を活かして防災力を高めること
- 地域活性化
- 地域の魅力とともに砂防施設等を活用して地域振興に寄与すること
- 全国の地震対応への寄与
- 今後の全国の土砂災害対応と砂防技術の継承に寄与すること