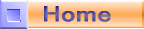![]()
〜稗田山崩壊地・金谷橋にて〜
平岩葛葉峠では雨は少々降っていました。
峠から下りると少し天気は持ち直しますが、
また、山を登ると雨が降ってきます。
次は、稗田山の崩壊地です。
山が晴れていたら、国道からも少しだけ見ることができます。
(中々気づきにくいかもしれませんけど・・・。)
でも、一番見える場所が金谷沢に架かる金谷橋です。
ただ、そこまでは途中工事(我々の事業以外の事業)が
行っていて、中々行けません。
上まで行って、稗田山を見ることができるのは「アルプス紀行」だけです(^_^)v
だだし・・・晴れていれば・・・・(T_T)
 |
|
| 左の写真は、金谷橋の中央にて、小谷村に在住する北村さんの解説を会員の方が聞いている様子です。 右の写真は、金谷橋から浦川の上流を見た写真です。 両方の写真に言えることですが、霧があって全く辺りは見えません(*_*) まるで、わざと私たちに見せないような感さえあります。 実は言うと、稗田山崩壊には、非科学的な伝説があり、今も語り継がれているのです。 |
|
稗田山崩壊跡は、日本の三大崩壊地の一つと言われています。
(ちなみにほかの二つは富山県の鳶山崩れと静岡県の大谷崩れです。)
もちろんここで言う崩壊地とは、何らかの原因で土砂崩れや地滑りなどで崩れた跡のことですが、
他の二つについては、主に地震が原因だったようです。
しかし、この稗田山に関しては、突如いきなり崩壊したというのですから、
住民の方は、さぞ驚いたことでしょう。
 |
晴れた日の稗田山崩壊地です。 緑がなく土砂が次々と崩れています。 実際行ってみると、さらにその崩壊の すさまじさが分かると思います。 なぜならば、崩壊はこの写真だけじゃ なくほぼ180度に渡って崩れている からです。 この日はちょっと前まで雨が降ってい ました。 写真の沢を見ると、水が茶色になって いるのがわかります。つまり、それだけ 崩れて水が濁っているということです。 |
 |
一人の女性とは、幸田文さんという方です。 明治の文壇「幸田露伴」の娘さんにあたる方です。 幸田文さんの代表作の一つ「崩れ」は砂防事業で働く方にとってはバイブルとも言える作品ではないでしょうか。 左の写真は、幸田文さんの文学碑で「歳月茫茫」碑と銘しています。 |
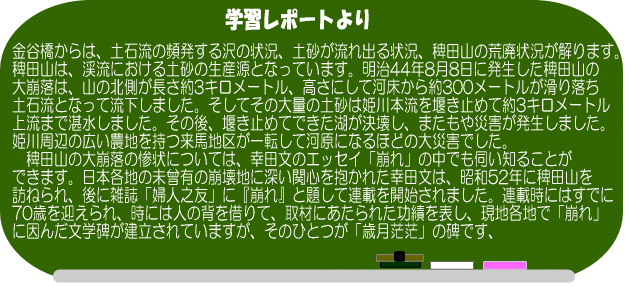
![]()
| ●小谷村は高い山々に囲まれ、いつ災害が起こるかわからないところであ●残念ながら雨と霧で山崩れ現場は見られませんでしたが、大変な災害だったものと少しは感じ取れました。 ●稗田山の崩れは長雨でもなく集中豪雨でもない。お天気続きの中での土石流と聞いてこの地域の地質のもろさ、地形の急勾配、前回勉強したぼろぼろの特徴が出ていると思えたし、砂防の大切さを痛切に感じたし、遠い地区の話ではなく、人事と思えない。 ●直接的な原因も無く大崩落をして、その副次的要因も加わり小谷一帯に大災害を引き起こした稗田山の崩壊地を立体的に一望できるこの金谷橋で見たかったけど、あいにくの雨で全く見ることができず残念でした。天気のよい日に是非再訪したいと思っています。できれば稗田山登山も。 ●想像を絶する崩壊に驚くばかりでした。それにしても地形が変わってしまう程の災害に当時の人々の思いは私の思いを遙かに超えるものだと思います。そして今も、土砂との戦いであることに、土地の方々の砂防への想いは計りしれないものだと感じます。 ●ここは日本か? アマゾンの奥地ではあるまいかと想わせるような壮絶な崩壊現場に案内されてもう絶句。小雨の状況ではあったが十分その風景は全国有数の崩落地を想わせるものであった。金谷橋に立ち上から下へと目を何度となく注ぎ小説家幸田文が随筆『崩れ』を書いた同じ場所にいるのだと心に言い聞かせた。 ●金谷橋は古いが立派に想えた。長く使えると思う。土砂が、毎日流れ出す。最高20メートルくらいの土砂により河床が高くなることが解った。 ●濃霧で視界が見えないのが残念でした。山の崩れを見ると河川の改修と砂防堰堤の工事は必要だと思いました。 ●今回一番期待していた場所でしたが、稗田山が見られなくて残念でした。幸田文さん、青木奈緒さんの本を読んで一度は見たいと思っていました。残念です。工事をしているところがありましたが、危険な場所で働く人たちのご苦労を想いました。 ●車の故障と天候の為、稗田山大崩壊の実態は目にすることができなかったが、小谷村の北村先生の説明によりそのすさまじさの一端を知ることができた。北村先生のように御土を愛し、語り部となる人を大切にしたいものである。松が峰の頂上にあるという張り出してきた石を観てみたいと思った。 ●金谷橋から観た稗田山は観る事が出来なかったのがとても残念だった。目前に急流な滝のように流れている沢を観て一瞬驚いたが、それが崩壊したら……。砂防堰堤がなかったらやはり土砂災害を繰り返すのでは……。現場を観て恐ろしさを感じた。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
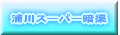 |
 |
 |
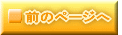 |
 |