
![]()
〜砂防講座「姫川流域で発生した災害を振り返る」植野事務所長より〜
松川を見終わって、そろそろ12時近くになりました。
それでは、本日の昼食場所へ向かいたいと思います(^o^)
場所は、小谷村にある道の駅「小谷」です。
ここは、大変にぎやかな場所で、我々職員も姫川管内にくるときはいつもここで昼食をとります。
あと私は入ったことはありませんが、お風呂もあるんです。
いたせりつくせりの道の駅です。
この道の駅では、恐竜のモニュメントもあります。
結構楽しい道の駅ですね。
 |
食事中の風景です。 やっと一休み(^_^;) ここまでケガなくこれてよかったです(^_^)v |
| 食事も終わって、砂防講座が始まります。 でも、その前に小谷村の小林村長さんのご挨拶をいただきました。 小谷村は、もともと地質が弱いところにあり、昔から災害に悩まれ続けてきました。 小林村長さんの言葉にもその大変さがにじみ出てくるようです。 |
 |
次は砂防講座です。
講演者は、当事務所長の植野です。
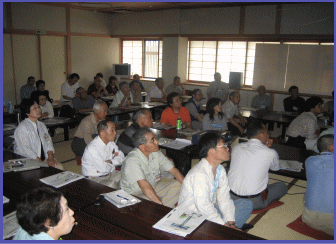 |
皆さん、真剣に聞いてます。 講座内容は10年前の小谷村を襲った「7・11水害」についてです。 また、岡谷市など諏訪地方を襲った「平成18年7月豪雨」についても、状況が分かる段階までで、講座を行いました。 |
| 右の写真は、講演者の当事務所長植野です。 パワーポイントを使った講座です。これからも、一般市民の方に理解しやすいよう、考えていきたいと思いますので、宜しくお願いします<(_ _)> |
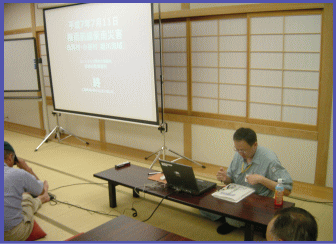 |
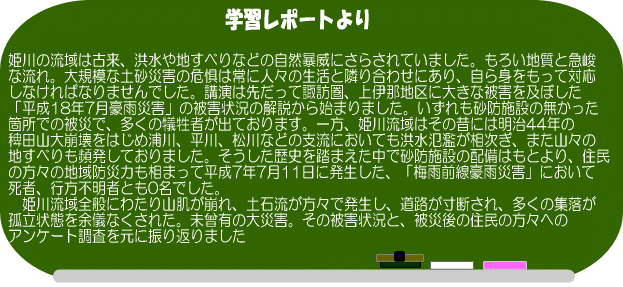
![]()
| ●小谷村は高い山々に囲まれ、いつ災害が起こるかわからないところである。要注意の場所である。 ●姫川沿いの特に小谷のような場所に昔から人が住み続けたのは驚きです。古人を引きつけるものがあったのでしょうね。現代人の知恵は自然の猛威をある程度コントロールできるようになりましたが、まだまだ自然の力はあなどれないのでは……。 ●昔からたくさんの災害にあわれたことを再認識し、自然と共に生活する姫川流域の方々のたくましさを感じました。 ●平成7年の梅雨前線に集中豪雨で姫川流域が大量の土砂を伴った大洪水の被害に遭われたとのことであるが、自然の力にはどうしようもない事もあるが、人間の力で元の姿に復興したということで人間の偉大さを感じた。 ●最近起きた中央道沿いの被害の様子がよくわかった。砂防工事の大切さをあらためて感じました。 ●土砂災害と砂防事業について過去の災害から学ぶことができた。法令、条例で危険地帯に人が住まないようにネットをかけるのはどうか。 ●講座の前の小谷村長の話、堰堤を作ることによって災害を防げるのではないか、ハード面で支えてくれて助かっているとの話、身につまされる思い、そしてご苦労を知りました。 |
![]()
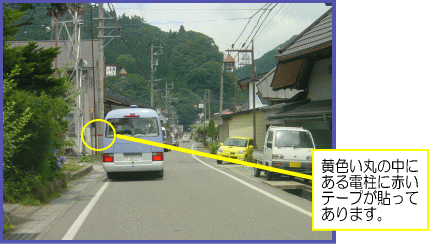 |
| 上の写真にある赤いテープが見えますでしょうか? これは、明治44年に稗田山が崩壊したときにできた天然ダムの水がここまで来ましたということを示したテープです。(この写真は小谷村にある下里瀬と言う場所です。) となりのバスは「アルプス紀行」の1号車のバスですが、その半分の高さくらいまで水が来たと言うことです。 新潟県中越地震で芋川も川が河道閉塞し、天然ダムが形成されましたが、小谷村でも過去に同じようなことが起きたのです。 二度とこんなことはないことを願うばかりです。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
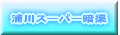 |
 |
 |
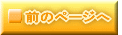 |
 |