よくわかる「砂防」 - 土砂災害のいろいろ
土石流(どせきりゅう)

山や川の石や土砂が大雨などでたくさんの水と共に津波のようにおそってくることで、むかしは山津波(やまつなみ)とも呼ばれてました。
土石流は、時速20~40キロメートルものスピードで何トンもある大きな石が流れてくることもあるため、その被害(ひがい)がとても大きくなります。土石流による災害は、急な谷川や流れが谷から扇状地(せんじょうち)へ流れ込む出口でよく発生します。
地すべり(じすべり)

地層(ちそう)は、性質のちがう土や石が積み重なってできています。ところが、地下水や雨水が地面にしみこみ、それが粘土のような滑りやすい層や弱い層に達すると、その上の層がすべり台のようにそっくり滑って崩(くず)れてしまいます。これを地滑り(じすべり)といいます。
ふだんは、1日に数ミリほどのゆっくりしたスピードで移動しますが、とつぜん急スピードで移動することがあるため、ゆだんできません。広いはんいで地面がすべり、そのときに押し出された土砂や、移動そのものの動きによって家や道路が被害をうけます。
崖崩れ(がけくずれ)
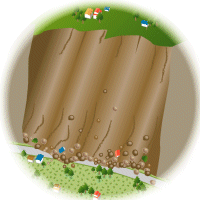
がけくずれは、かたむきが急な斜面(しゃめん)が大雨や地震(じしん)などで突然(とつぜん)崩れるもので、くずれた土砂は、斜面の高さの2~3倍の距離に達することがあります。がけくずれは、地すべりとちがって突然(とつぜん)発生し、そのスピードが速いため家や人に被害(ひがい)をおよぼすことがあります。
