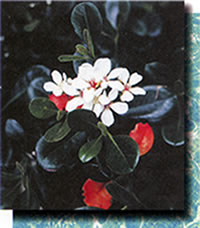 |
 |
|
|
 |
| シャリンバイの変種で、最も耐寒性が強く、日本海側は山形県温海町が北限であるが、富山県には自生しない。海岸の砂地に生育する高さ2m内外の常緑低木で、半球形の樹形となる。春にはウメのような白い小さな花をつけ、秋には実が黒く熟する。耐潮性と耐寒性に優れ、大気汚染にも強い。日当りのよい場所であれば、土壌は問わない。成長は遅く萌芽力はないので、剪定は行わない方がよい。 |
|
 |
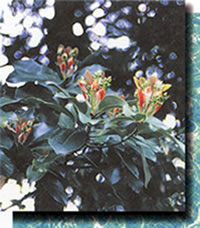 |
 |
|
|
 |
| 常緑広葉樹の代表種。自然樹形が美しく、紅橙色の芽出しも特徴的である。クスノキの高木としては寒さに強く、日本海側では、山形県まで分布し、富山県内では朝日町宮崎と氷見市の海岸に原生林が残されている。宮崎の樹叢は県の天然記念物に指定されている。また入善町のサワスギ林にも整備される前にはタブノキの混生がみられた。耐潮性・耐寒性に優れ、海岸地方では防潮・防風林としても利用する。やや陰樹的性質で、幼樹はかなりの日陰でも生育できる。深根性のため移植はやや困難で、また樹皮が剥がれやすいために移植には注意が必要である。 |
|
 |
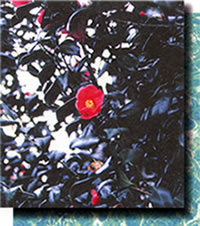 |
 |
|
|
 |
| 暖帯林の代表的な構成樹種であるが、青森県(日本海側では秋田県)まで分布がある。寒さに強く、海岸沿いによく分布し、潮風にも強い。数多くあるツバキの園芸品種の原種である。陰樹で成木、幼木とも耐陰性は強いが、植栽する場合は向陽地でもよく育つ。肥沃でやや湿潤な土壌が適する。黒部川左岸の荒俣地内に残る「村椿」の地名はヤブツバキの群生地を示す「群れ椿」から転化したものである。 |
|