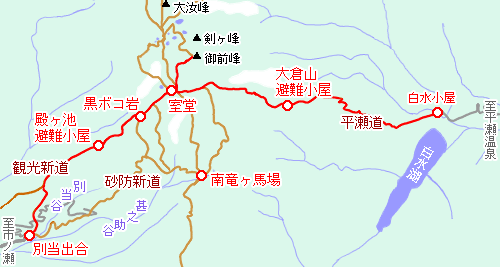
手取川の源流域と、普段眼にすることのない岐阜県側の白山を観察するため、観光新道〜平瀬道のルートで白山登山を実施しました。
赤いラインが特派員のたどった登山道です。
(石川県側のルートはこちらのマップでも確認できます。)
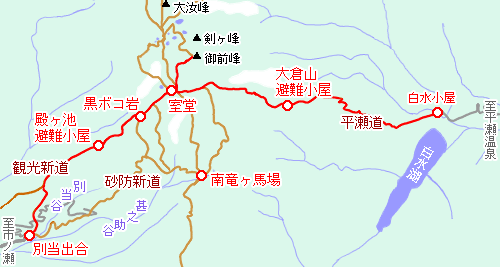
|
|

|
|

|
ぬかるみが激しい登山道の状態。 |

|
|

|
|
 |
 |
アオノツガザクラ |
ハクサンフウロ |
 |
 |
ミヤマダイモンジソウ |
オタカラコウとイブキトラノオ |
 |
 |
コバイケイソウ |
タカネマツムシソウ |

|
|
|
室堂周辺で見られた高山植物。
|
|
 |
 |
イワギキョウ |
クルマユリ |
 |
 |
ニッコウキスゲ |
ヨツバシオガマ |

|
|

|
|

|
|

|
|

|

|

|
|

|

|
|

|
|

|

|
|

|
|

|
|