1.一般国道157号鶴来バイパス道路緑化懇談会資料(第2回)
自然植生の緑地を整備するにあたっては、本来なら百年近くの年月が必要であるが、この計画では20〜30年後を目標としている。また、ここで計画する自然植生の多くは、その成長過程で強い日当たりを嫌う性質がある。
このような条件を踏まえ、本計画では、20〜30年後に自然植生による緑地を概成するために、以下の工法が考えられる。
これら工法の中から、本計画では以下の理由により、[1]「先駆樹木(幼木)と自然植生の混植」及び[2]「自然埴生のみによる直接的育成」を主体に計画することとする。
| [1] 先駆樹木(幼木)と自然植生 (幼木・種子)の混植 |
[2] 自然植生(幼木)のみによる 直接的育成 |
[3] 先駆樹木(高木)と 自然植生(幼木)の混植 |
|---|---|---|
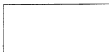 |
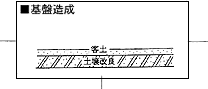 |
 |
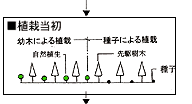 |
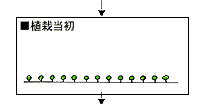 |
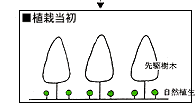 |
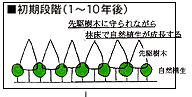 |
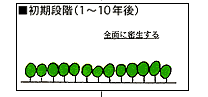 |
|
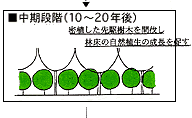 |
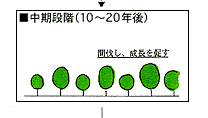 |
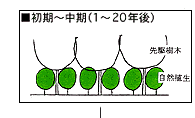 |
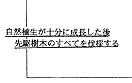 |
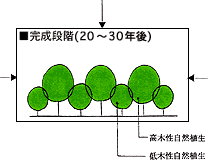 |
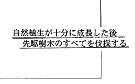 |