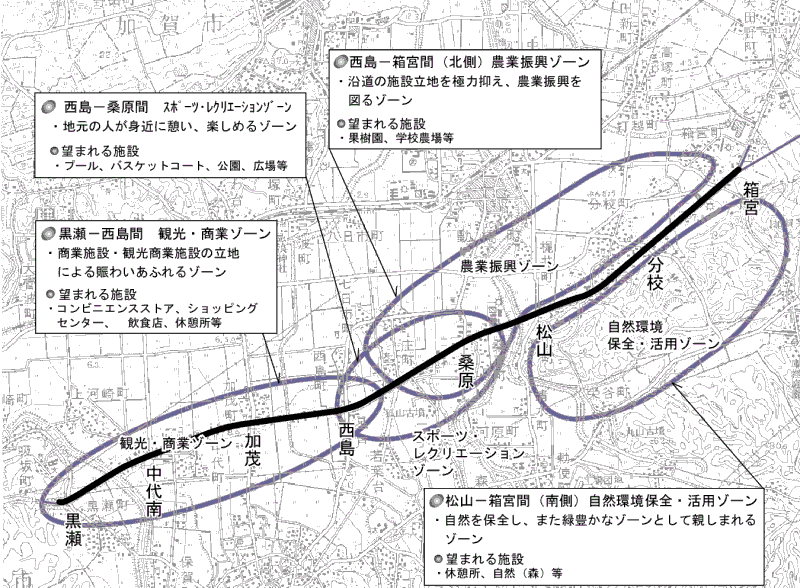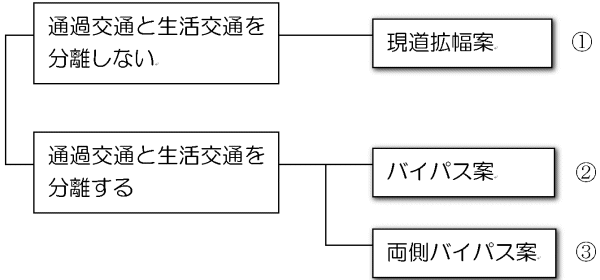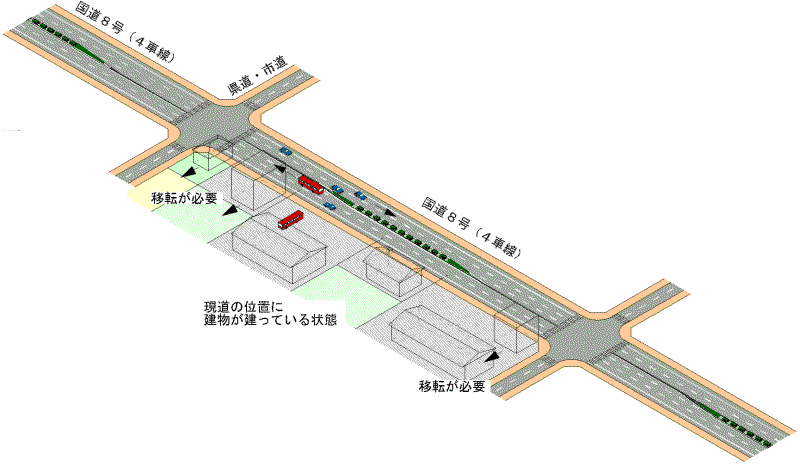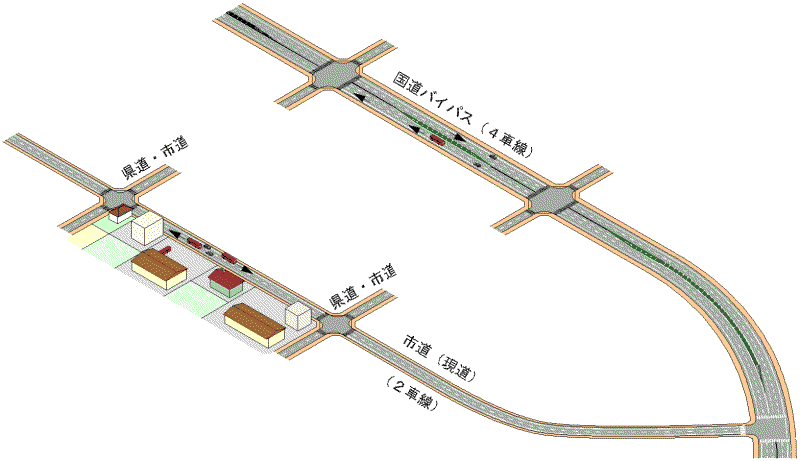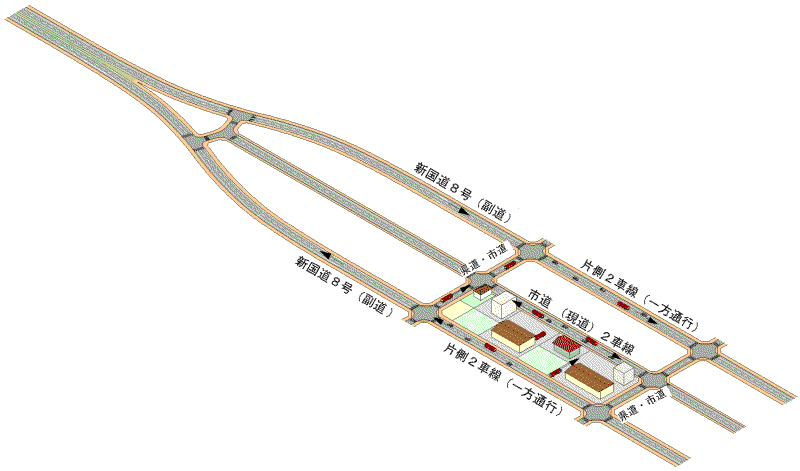<< 前へ[資料の先頭へ][資料の一覧へ]次へ >>
2.まちづくり・みちづくりの方向
(1)まちづくりの方向
これまで出された考える会での意見や子供たちの提案をもとに、まちづくりの方向性を整理すると、現状の土地利用状況を踏まえて、商業集積を図るゾーンと、残された農地や自然を保全・活用していくゾーンとに分けた土地利用を行うことが望まれていると考えられます。
■沿道まちづくりの方向性■
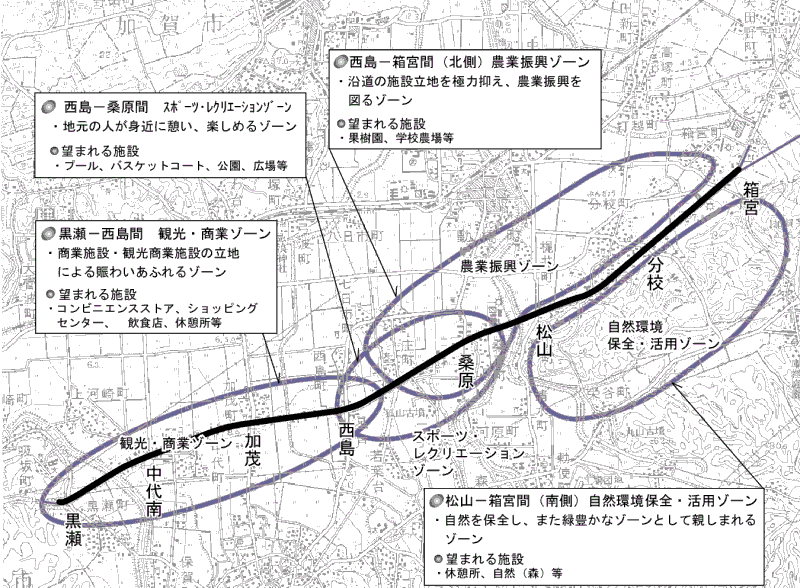
[top]
(2)みちづくりの方向(代替案)
みちづくりの方向としては、これまで出された数多くの意見をまとめると、以下の3つの手法のいずれかになると考えられます。
【みちづくりの手法】
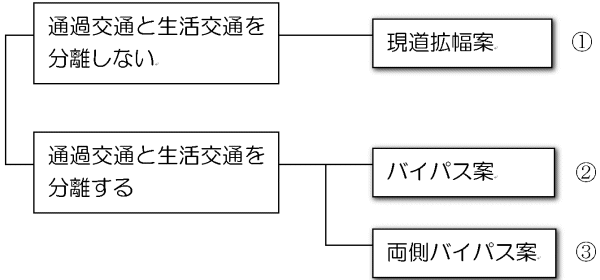
【イメージ】
① 現道拡幅案
現道をそのまま4車線に拡幅します。
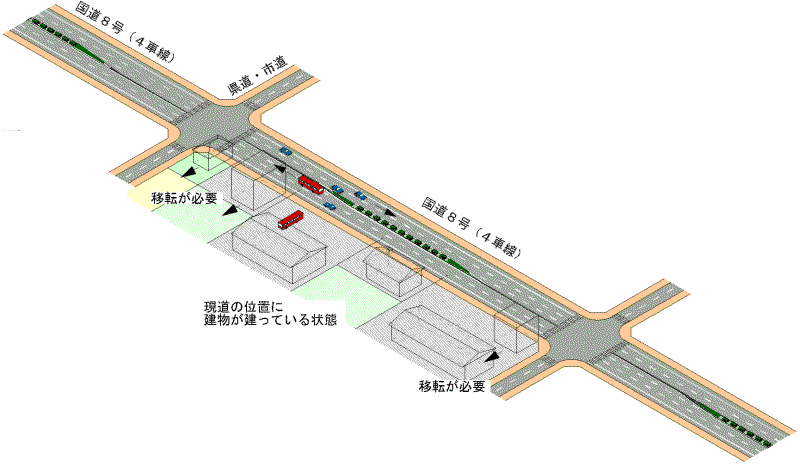
※ロータリーや裏道の整備により、中央分離帯設置による沿道施設等への出入りの不便さは緩和できます。
[top]
② バイパス(一部バイパス)案
現道はそのままにし、バイパスを整備します
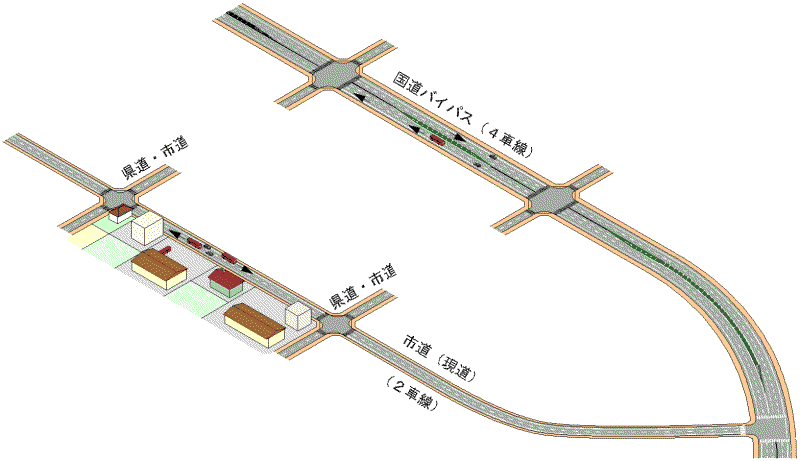
[top]
③ 両側バイパス案
現道はそのままにし、現道の両側にバイパス(一方通行)を整備し、通過交通と生活交通(沿道施設利用車)を分離します。
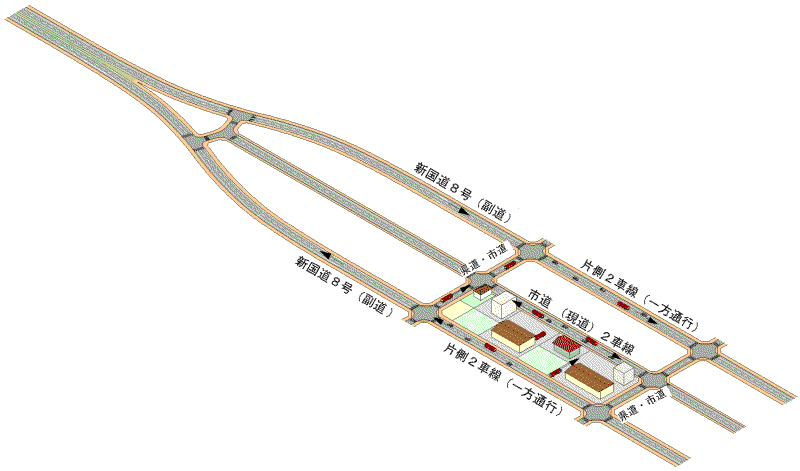
※通過交通はバイパス(新しい国道8号)を利用することになります。(両側一方通行)
[top]
【各案の比較】
①現道拡幅案、②バイパス(一部バイパス)案、③両側バイパス案の各案について、メリット・デメリットを比較検討しました。
■ 道路整備案のメリット・デメリットの比較 ■
| |
①現道拡幅案 |
②バイパス(一部バイパス)案 |
③両側バイパス案 |
| メリット |
- 拡幅(4車線化)に伴い混雑が解消され、円滑な通行が行えます。
- 中央分離帯の設置により安全な通行が行えます。
- 拡幅に伴う街並みの再編により、良好な景観形成が可能となります。
- 比較案の中で最も用地取得面積が少なくて済みます。
- 工事が完成した区間から部分的に開通することができ、効果が早く現れます。
|
《バイパス部分》
- 通過車両は、バイパスを利用することにより、円滑に通行できます。
- バイパス沿いで新たなまちづくりが可能です。
- 比較案の中で、最も事業費が少なくて済むと考えられます。
《現道部分》
- 交通量の減少に伴い混雑が解消され、円滑な通行が行えます。
- 交通量が少なくなり、道路の安全性が高まります。
- 中央分離帯のない現道は現状のまま残るため、対向車線側への移動は現状の通り可能です。
|
《バイパス部分》
- 通過車両は、バイパスを利用することにより、円滑に通行できます。
《現道とバイパスに挟まれた部分》
- 現道とバイパスに挟まれた土地は、現道とバイパスの両側からアクセスできることになり、利便性が高まります。
- まとまって使える土地ができ、その土地利用を一体的に規制・誘導することにより、良好なまちづくりが行えます。
《現道部分》
- 交通量の減少に伴い混雑が解消され、円滑な通行が行えます。
- 交通量が少なくなり、道路の安全性が高まります。
- 中央分離帯のない現道は現状のまま残るため、対向車線側への移動は現状の通り可能です。
|
| デメリット |
- 中央分離帯が設置されるため、主要交差点以外で右折できないことにより、対向車線側への移動が制限されます。
- 交通量の増加や走行速度の上昇に伴い、騒音・振動の影響が大きくなります。
- 拡幅に伴い、建物の移転が必要な方が出てきます。
- 工事中は、沿道の方の協力が不可欠です。
|
《バイパス部分》
- 中央分離帯が設置されるため、主要交差点以外で右折できないことにより、対向車線側への移動が制限されます。
- バイパス沿いでは、新たに騒音・振動の問題が発生します。
- まとまった用地取得が必要となります。また、一部で建物の移転が必要な方が出てきます。
- バイパスによる地域分断や農道の遮断が生じます(代替機能は確保されます)。
《現道部分》
- バイパス沿いに施設整備が進むと、現道沿いの施設との競合が生じます。
|
《バイパス部分》
- 一方通行となるため、対向車線側への移動は市道等を経由することが必要になります。
- 一方通行のため、通常追い越し車線である右折車線より施設に出入りすることとなり、円滑な走行が行いにくくなります。また、右側の施設に出入りするときは、特に他の車両に対する注意が必要です。
- まとまった用地取得が必要となります。また、一部で建物の移転が必要な方が出てきます。
《現道とバイパスに挟まれた部分》
- 道路の構造上、現道とバイパスとの距離は最低100m以上確保する必要があり、これを前提とした土地利用を行う必要があります。
- バイパスと交差する市道等では、交差点が2ヶ所増え、交差点が近接して3ヶ所連続することになります。
- バイパス沿いでは、新たに騒音・振動の問題が発生します
- バイパスによる地域分断や農道等の遮断が生じます(代替機能は確保されます)
《現道部分》
- バイパス沿いに施設整備が進むと、現道沿いの施設との競合が生じます。
|
| 課題 |
- 拡幅場所の選定(片側又は両側)
- ロータリーや裏道の整備等
- 拡幅後の沿道の土地利用
|
- バイパス設置区間の選定
- バイパスルートの選定
- バイパス沿道の土地利用
|
- バイパス設置区間及びルートの選定
- 現道とバイパスに挟まれた部分の土地利用計画の策定
- 土地利用計画の実行(バイパス整備と同時に行う必要があります)
|
注)この内容は、今後「検討会」で詳細に検討されます。
<< 前へ[資料の先頭へ][このページの上へ][資料の一覧へ]次へ >>