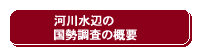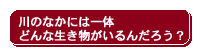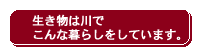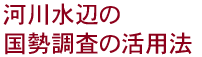
河川水辺の国勢調査結果は、河川事業の推進のための基礎資料として活用されますが、
その活用事例を一部紹介します。
 自然石を配して自然との調和および水生物の生息環境に配慮した例
植生を回復させるために覆土した例 |
■多自然川づくりの推進 生物の良好な生息環境に配慮し、あわせて美しい自然環境を保全あるいは創出する目的で、「多自然川づくり」が推進されています。 その計画・施工にあたっての基礎資料として活用されています。 ■パンフレット等によるPR パンフレット等により川の生物を広く一般に紹介しています。また、標本の展示等も計画されています。
■問い合わせ先
■河川水辺の国勢調査年鑑の発行 (財)リバーフロント整備センターの編集により、全国の調査結果を年鑑の形で発行しています。 |
■アドバイザーから一言
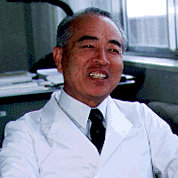 本間義治 新潟大学名誉教授 |
河川という限られた範囲ですが、これまでにない大きな規模の調査でした。 調査方法も年を重ねるごとに確立され、マニュアルが整備されるとともに精度が向上してきました。 有能な地元の調査者にとってもこの調査はいい機会で、その質を向上させることにもなったわけです。
思わぬ発見があり、生物地理学・分布学、あるいは分類学の上でも貴重なデータの蓄積ができました。
今後も引き続き調査を続けることが、この調査の価値をさらに高めることになります。これからの課題は、これらの資料の保存、標本庫あるいは収蔵室の充実です。研究者のためだけではなく、一般の方々のためにも、きちんとした形で標本や資料を残し公開展示することが必要です。 一例ですが、河畔林を大事にし、瀬と淵をつくり、魚が行き来する川づくりを進めていくことが、魚だけでなく他の生物の環境にとっても好ましいものとなり、自然を戻すことになります。これからは、河川管理者だけでなく地元の住民も一緒に移り変わる自然、河川を管理していく時代です。 |