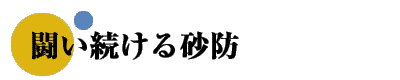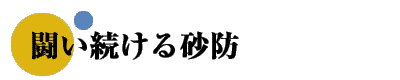土砂との闘い
昭和42年の羽越災害では河川の氾濫と土石流の発生により、死者・行方不明者136名を数え、当時の金額で被害総額は約1,115億円にも上りました。最近では、平成7年7月の豪雨によって土石流が発生し、流出した土砂は姫川の河床を著しく高め、家屋の流失だけではなく、国道や鉄道などのライフラインにも著しい被害を及ぼしたことは記憶に新しいところです。
こうした災害を防ぐための近代的な砂防事業は、明治時代に始まっています。北陸地域では、明治14(1881)年に信濃川(犀川)の上流(現在の松本砂防工事事務所管内)で国による直轄砂防事業が着手されています。また、砂防法にもとづく補助砂防事業も、明治31(1898)年より長野県で開始されました。大正7年に完成した牛伏川のフランス式階段工は、現在も機能を果たしているうえ、自然と巧みに調和したその景観は、文化財としても高い価値を持っています。
その後、大正8年に神通川、同15年に常願寺川、昭和2年に手取川、12年に信濃川下流(魚野川、清津川など)、36年に黒部川、37年に姫川、44年に飯豊山系でそれぞれ直轄砂防事業に着手してきました。
一方、地すべり等防止法にもとづく直轄地すべり対策事業についても、昭和36年に手取川、56年、平成8年に阿賀野川で着手しています。
なお、砂防事業は、中山間地の社会基盤整備に重要な役割を果たしていることから、地域活性化の支援策としての期待も高まってきています。
|
|

土石流で埋まった新潟県関川村の湯沢温泉地区(昭和42年羽越災害)
|