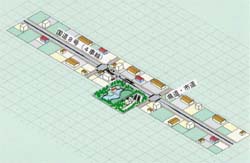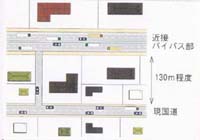(4)検討のまとめ
●検討のまとめ(第4回検討委員会(平成13年2月28日)の比較検討表を基に、新たな要因などをふまえて再整理した)
| 項目 | 観点 | 現道拡幅案 | 近接バイパス案 | |
|---|---|---|---|---|
| まちづくり | 賑わい | ○拡幅に伴う資金を再投資して、現在の賑わいを活かしつつ、快適で魅力的な沿道景観を形成できる可能性がある。 ○拡幅した際に空き地等となった土地に、新たに商業施設が出店する可能性がある。
△不整形や狭小な土地が発生する可能性がある。 △拡幅を契機にこの地区から撤退する商業者が現れる可能性がある。 |
○現道の賑わいを残しつつ、現道と近接バイパスが一体となって面的なまちづくり(約23ha)を行うと、賑わいのあるまちが形成される可能性がある。 ○現国道とあわせて回遊性が高まる可能性がある。 ○道路に面する土地が増え(道路延長約1,900m)、良好な市街地が形成される可能性がある。
△一体的なまちづくりを行わないと、道路に接しない土地が発生したり、不整形や狭小な土地が発生する可能性がある。 △バイパス山側については、優良農地のため、農地転用が難しい。 |
|
|
||||
| 評価 | ○ | ○ | ||
| 道の駅 |
|
|||
| 評価 | ○ | ○ | ||
| 景観 |
|
|||
| 評価 | ○ | ○ | ||
| 沿道商業施設 | ○拡幅に伴う資金を再投資することができる。 ○拡幅した際に空き地等となった土地に、新たに商業施設が出店する可能性がある。 ○交通量の増加に伴い、利用者の増加が見込める。 △拡幅を契機にこの地区から撤退する商業者が現れる可能性がある。 △現道拡幅の工事期間中は、商業活動に影響が出ることが考えられる。 △中央分離帯の設置により、沿道施設への出入りは片側のみとなる。 △駐車場や販売促進の共同化、街並みの統一等の一体的なまちづくりや魅力的な商業施設の形成を行っていかないと、小規模の商業施設は淘汰される可能性がある。 個々のまちづくり
⇒ 一体的なまちづくり
|
○現道と近接バイパスが一体となったまちづくりが行われると、回遊性が高まった、賑わいのあるまちが形成される。 ○バイパス区間の現道では、工事の影響をほとんど受けずに営業が行える。 △一体的なまちづくりが行われないと、近接バイパス部に新たに立地する沿道施設と現道との競合が生じる。 △現国道へのスムーズな誘導が行われないと、現国道での利用者は減少する。 △現道拡幅部、近接バイパス部では、中央分離帯の設置により、沿道施設への出入りは片側のみとなる。
|
||
| 現道拡幅案・近接バイパス案いずれの案でも、一体的なまちづくりを行っていかないと淘汰される可能性がある。 | ||||
| 評価 | ○ | ○ | ||
| 自然環境 | 近接バイパス案の方が開発する範囲は広いが、現道拡幅案・近接バイパス案のいずれの案とも現在の自然環境を大きく変えない。 | |||
| 評価 | ○ | ○ | ||
| 農業 | ○農地の保全が行える ○農地の集約化を図ったり、主体となって活動する中核農家が確保できれば、農業の振興を図ることは可能である。 △農耕車等での道路横断が限定される |
○農地の集約化を図ったり、主体となって活動する中核農家が確保できれば、農業の振興を図ることは可能である。 △農耕車等での道路横断が限定される。 |
||
 現道拡幅案の方が農地の保全面積は広いが、現道拡幅案・近接バイパス案のいずれの案でも、農業の振興を図ることは可能である。 |
||||
| 評価 | ○ | ○ | ||
| 子ども | 自転車道が現道拡幅案・近接バイパス案のいずれの案でも整備され、歩行者と自転車が分離されることから、安全な環境が確保される。 | |||
| 評価 | ○ | ○ | ||
| 若者 | 現道拡幅案・近接バイパス案のいずれの案でもまちづくりによる賑わいの場が形成されれば、若者が遊べる場は確保できる。 | |||
| 評価 | ○ | ○ | ||
| まちづくりの実現性 | ○沿道商業者の多くが現道拡幅案に賛成しており、現道拡幅案となった場合には、まちづくり活動の主体となって事業推進を図ることや、中央分離帯の設置に賛成し、さらに、海・山のどちら側に拡幅されても賛成する等の、積極的な発言をしている。 ○片側に大きく拡幅されることによって(最大20m程度)、沿道施設の大半が建替えを行う必要があり、拡幅される側において新たなまちづくりを行うことができる。 ○拡幅に伴う資金を再投資することができる。 |
△現時点では、まちづくりを主体的に行って行く組織・人材が明確になっていない。 △一体的なまちづくりには、土地区画整理事業などの基盤整備が必要であり、土地区画整理事業では地権者や事業者にとって実現するための不確定要素が多い(減歩率が高い、事業費が高い、保留地が売れないなど)。 △長引く不況の中で、新たに施設投資を行おうとする事業者が少ないと考えられる。 |
||
|
||||
| 評価 | ○ | △ | ||
| 事業費見込み | 道路本体 | 約240億円(うち用地・補償費約160億円 | 約220億円(うち用地・補償費約140億円) | |
| (桑原〜中代南) | 約150億円(うち用地・補償費約110億円) | 約130億円(うち用地・補償費約90億円) | ||
| 周辺施設 | 約30億円(Uターン路と道の駅) | 約30億円(区画道路と道の駅) | ||
|
||||
| 評価 | △ | ○ | ||
| 項目 | 現道拡幅案 | 近接バイパス案 | |
|---|---|---|---|
| 自動車利用者 | ○4車線化によって渋滞が緩和され、走行性や安全性が向上する。 ○道の駅の整備によって、休息の場が確保される。 △生活交通と通過交通が混在する。 △交通量の増加や中央分離帯の設置により、道路横断が限定される。
|
○4車線化によって渋滞が緩和され、走行性、安全性が向上する。 ○道の駅の整備によって、休息の場が確保される。 ○近接バイパス部では生活交通と通過交通が分離される。 △交差する道路では、近接バイパス部で新たに交差点が近接して1ヶ所増える。 △現道拡幅部、近接バイパス部では交通量の増加や中央分離帯の設置により、道路横断が限定される。
|
|
| 現道拡幅案・近接バイパス案のいずれの案も、4車線化によって渋滞が緩和され、走行性や安全性が向上する。 | |||
| 評価 | ○ | ○ | |
| 歩行者・自転車 | ○歩道や自転車道の整備により安全性、利便性、快適性が高まる。 |
○近接バイパス部では歩道や自転車道が整備され、安全性、利便性、快適性が高まる。 △現道では、現況を大きく改善することはできないが、自動車の交通量が減少することから安全性は向上する。 |
|
  現道拡幅案・近接バイパス案のいずれの案も歩道や自転車道が整備されることから、歩行者・自転車の安全性、利便性、快適性が高まる。 |
|||
| 評価 | ○ | ○ | |
| 沿道環境 | ○2列の植栽帯が海・山の両側に整備される △交通量の増加に伴い、騒音、振動の影響が大きくなる。 |
○2列の植栽帯が海・山の両側に整備される。 △現道では交通量の減少に伴い、騒音、振動の影響が小さくなるが、近接バイパス部では新たに影響が生じる。 |
|
|
|||
| 評価 | ○ | ○ | |
| 観点 | 現道拡幅案 | 近接バイパス案 |
|---|---|---|
| 第6回・7回検討委員会での主な意見
○:賛成意見 △:反対意見 |
「早期に事業着手すべき」という意見が多数挙げられている。 | |
○Uターンできる場所が整備されるなら、現道拡幅でよい。 ○現道拡幅案は、既に一部の区間が都市計画決定されている。 ○沿道商業者は全員一致して、現道拡幅を行っていただきたいと考えている。 △事業費が近接バイパス案より高い |
○加賀市の活性化、発展が期待できる。 ○自動車の通行性がよい、近接バイパス案がよい。 ○近接バイパスと現道との間を面的なまちづくりを行って、観光客を引きつける核をつくることができる。 ○近接バイパス案は、現道拡幅よりも事業費が安い。 ○近接バイパス案は、土地の有効利用や車や人の循環性がよくなる。 △まちづくりのための事業主体が必要ではないか。 △現道から1〜2mはずれても、現道の商売に影響する。 △近接バイパス案では、バイパスが壁となり山側からの車の流れが現道へ入りにくくなる。 △近接バイパス案では、現道沿いの資産価値が下がる。 |
|