土砂災害学習コーナー
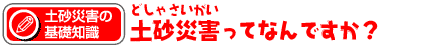
どんな対策をしているのですか?
土石流対策
土石流は谷川などにたまった石や土砂が、大雨がきっかけで流れ出て起こるので、山の斜面が崩れて石や土砂がたまらないように、山に木を植えて崩(くず)れるのを防ぎます。また土石流を受け止めて人の命や家を守る砂防えん提(さぼうえんてい)を作って防ぎます。
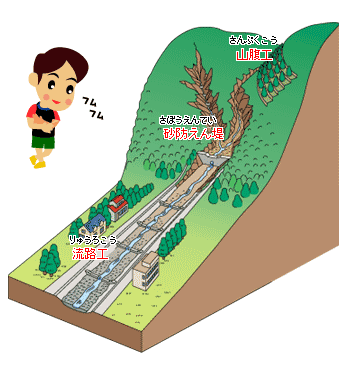
山腹工(さんぷくこう)
山腹の崩壊箇所で崩壊の進行を抑えるために行われる工事で、荒れた斜面を整え植物の種をまいたり、苗木を植えて緑化が図られています。土砂が川に流れ出るのを未然に防ぐ砂防工事です。

六九谷山腹工(富山県大山町)
砂防えん堤(さぼうえんてい)
砂防えん堤(さぼうえんてい)は土石流など大量の土砂が一度に流出したときに、一時的に土砂を堆積させ、その後の出水により徐々に流下させるはたらきをもっており、砂防施設では最も基本的なものです。
また最近では普段は土砂を貯めずに下流に流す透過型の砂防えん堤も造られています。

▲クローズ型 (黒又沢砂防えん堤)
(新潟県六日町)-

▲透過型(実川第1号砂防えん堤)
(新潟県鹿瀬町)
流路工(りゅうろこう)
急流河川では川底や川岸が浸食されて、その土砂が下流に流出し、氾濫・決壊することがあるので、浸食を防止し流路を安定させるため、流路工が施されます。特に河床勾配の強い急流部には床固工が階段状に施されています。

松川流路工(長野県白馬村)