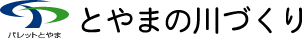 |
| 河川管理施設数と流量・水質測定箇所数 |
 |
| ※…揚水機場含む ( )…暫定 |
| 河川名 |
管理延長(km) |
堰 |
水門 |
樋門 |
排水機場※ |
流量観測箇所 |
水質測定箇所 |
| 常願寺川水系 |
21.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
| 神通川水系 |
48.1 |
1 |
2 |
8 |
0 |
6 |
8 |
| 庄川水系 |
26.1 |
0 |
0 |
4 |
1 |
3 |
3 |
| 小矢部川水系 |
37.4 |
1 |
0 |
27 |
(1) |
6 |
6 |
|
| 河川管理施設数と流量・水質測定箇所数 |
 |
| 常願寺川 |
| 常願寺川は、北アルプスの北ノ俣岳(きたのまただけ)(標高2,661m)を水源として、わずか56kmで日本海へ流れ出るという我が国屈指の急流河川です。そのため上流部の非常にもろい地盤条件と相まって、上流から流れ出す土砂の量が非常に多いと |
|
 |
| いう特徴があり、下流部においては川底が両岸の土地より高いという天井川を形成しています。また、急流による堤防破堤防止のため、いたるところに「水制」が見られるのも特徴のひとつです。 |
| 水源地及標高 |
富山県富山市(北ノ俣岳 標高 2,661m) |
| 流 域 面 積 |
368km2 |
| 幹川流路延長 |
56km |
| 想定氾濫面積 |
150km2 |
| 大臣管理区間 |
21.5km |
| 計 画 流 量 |
| 瓶岩地点 |
 |
基本高水流量 |
 |
4,600m3/s |
| |
|
計画高水流量 |
|
4,600m3/s |
|
| 既往著名出水量 |
| 瓶岩地点 |
 |
大正3年8月12日 |
 |
約3,000m3/s |
| |
|
昭和27年7月1日 |
|
約2,200m3/s |
| |
|
昭和44年8月11日 |
|
約3,970m3/s |
| |
|
平成10年8月11日 |
|
約1,700m3/s |
|
| 計画高水位勾配 |
下流1/477〜1/399
中流1/142〜1/76
上流1/68〜1/59 |
|
 |
| 神通川 |
| 神通川は、岐阜県の川上岳(かおれだけ)(標高1,626m)を水源として、飛騨地方から富山県の中央部を通って日本海へそそぐ長さ約120kmの一級河川です。上流部が日本有数の多雨地帯であるため、古くから度々洪水を引き起こしてきました。現在、 |
|
 |
| 富山市を中心とする氾濫域は、富山県の社会、経済、文化の中枢を担っているので、水害対策はもちろんのこと、親しみのある快適な河川空間の創造が期待されています。 |
| 水源地及標高 |
岐阜県高山市(川上岳 標高 1,626m) |
| 流 域 面 積 |
2,720km2 |
| 幹川流路延長 |
120km |
| 想定氾濫面積 |
123km2 |
| 大臣管理区間 |
本川25.2km 西派川2.4km 支川井田川14.8km
支川熊野川5.7km |
| 計 画 流 量 |
| 神通大橋地点 |
 |
基本高水流量 |
 |
9,700m3/s |
| |
|
計画高水流量 |
|
7,700m3/s |
|
| 既往著名出水量 |
| 神通大橋地点 |
 |
昭和33年7月26日 |
 |
約3,900m3/s |
| |
|
昭和36年6月27日 |
|
約3,600m3/s |
| |
|
昭和47年7月13日 |
|
約4,100m3/s |
| |
|
昭和58年9月28日 |
|
約5,700m3/s |
| |
|
平成10年4月15日 |
|
約2,950m3/s |
| |
|
平成16年10月21日 |
|
約6,460m3/s |
|
| 計画高水位勾配 |
| 本川 |
 |
下流1/1,198〜1/812 |
 |
中流1/537〜1/230 |
| |
|
上流1/190〜1/187 |
|
|
|
| 支川井田川 |
 |
下流
1/1,229〜1/353 |
 |
中流
1/231〜1/120 |
| 支川熊野川 |
|
上流
1/420〜1/190 |
|
|
|
|
| 庄 川 |
| 庄川は、岐阜県の烏帽子岳(えぼしだけ)(標高1,625m)を水源として、飛騨山地から数々の支川を併せて富山県に入り、砺波市、高岡市、射水市を経て、日本海へそそぐ長さ約115kmの一級河川です。流域には砺波平野が広がり、越中米やチューリ |
|
 |
| ップなど、多くの特産物を生み出しています。しかし、この恵みある流れも、ひとたび洪水になると多くの被害を流域にもたらします。現在、人々の暮らしを守る堤防や護岸の整備がすすめられています。 |
| 水源地及標高 |
岐阜県高山市(烏帽子岳 標高 1,625m) |
| 流 域 面 積 |
1,189km2 |
| 幹川流路延長 |
115km |
| 想定氾濫面積 |
234km2 |
| 大臣管理区間 |
26.1km |
| 計 画 流 量 |
| 雄神地点 |
 |
基本高水流量 |
 |
6,500m3/s |
| |
|
計画高水流量 |
|
5,800m3/s |
|
| 既往著名出水量 |
| 小牧地点 |
 |
昭和9年7月11日 |
 |
約3,400m3/s |
| 大門地点 |
|
昭和34年9月27日 |
|
約1,900m3/s |
| |
|
昭和51年9月11日 |
|
約2,700m3/s |
| |
|
昭和58年9月28日 |
|
約1,700m3/s |
| |
|
平成16年10月21日 |
|
約3,400m3/s |
|
| 計画高水位勾配 |
下流1/1,045〜1/723
中流1/437〜1/202
上流1/192〜1/147 |
|
 |
| 小矢部川 |
| 小矢部川は、富山県の大門山(だいもんざん)(標高1,572m)を水源とし、小矢部市、高岡市を経て、日本海へそそぐ長さ約68kmの一級河川です。急勾配の河川の多い富山県においては、比較的緩やかな川ですが、かつて庄川の支川として合流していた |
|
 |
| ころは、庄川の出水のたびに逆流が生じ、河口付近では伏木富山港を中心に、大きな被害が起っていました。そこで行なわれた大正元年(1912年)の庄川との分離以来、被害は減少し、地域発展の礎となっています。 |
| 水源地及標高 |
富山県南砺市(大門山 標高 1,572m) |
| 流 域 面 積 |
667km2 |
| 幹川流路延長 |
68km |
| 想定氾濫面積 |
65km2 |
| 大臣管理区間 |
本川35.4km 支川渋江川2.0km |
| 計 画 流 量 |
| 津沢地点 |
 |
基本高水流量 |
 |
1,300m3/s |
| |
|
計画高水流量 |
|
1,300m3/s |
|
| 既往著名出水量 |
| 西五位地点 |
 |
昭和28年9月25日 |
 |
約1,300m3/s |
| 津沢地点 |
|
昭和39年7月18日 |
|
約1,200m3/s |
| |
|
昭和40年9月18日 |
|
約1,200m3/s |
| |
|
平成2年9月20日 |
|
約950m3/s |
| |
|
平成10年9月22日 |
|
約920m3/s |
| 石動地点 |
|
平成10年9月22日 |
|
約1,300m3/s |
| 長江地点 |
|
平成10年9月22日 |
|
約1,590m3/s |
|
| 計画高水位勾配 |
1/2,760〜1/460 |
|
|
|