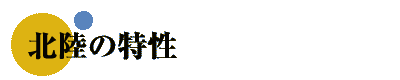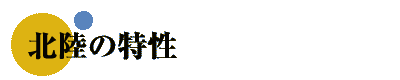厳しい自然環境
北陸地域の気候は、盆地部を除くと、多雨多湿の日本海型気候に分類されます。平均して1年間に2,500mmを越える雨が降り、全国平均の1,700mmあまりを大きく上回っています。なかでも、北アルプスなどの嶮しい山岳地帯では4,000mm以上にも達しています。また、この雨の量の約30%が冬季の雪であることも北陸の特徴です。
糸魚川と静岡を結ぶ大構造線、いわゆるフォッサマグナの西側には3,000mに及ぶ高峰が連なっています。また、火山地帯が広く分布し、その地質は脆く、弱いため、雨が降ると、山腹の崩壊、地すべり、土石流などが発生するとともに、これらにより多量の土砂が河川に流れ込み、河床の上昇にともなう洪水流の氾濫などを引き起こします。これらは、いずれも急激に、かつ巨大なエネルギーを持って下流のまちや農地を襲うため、人の命や生活基盤に直接関わる大きな被害をもたらすことが多くあります。また、土砂災害は、高齢化・過疎化が進み、いわゆる災害弱者の多い中山間地に多く発生することもひとつの特徴です。
さらに、北陸の厳しい自然環境は海岸部にも及びます。11月頃から3月頃までの冬期間は、西高東低の気圧配置から生じる季節風が海風となって日本海側の沿岸部で吹き荒れて、しばしば高波が襲来し、被害をもたらします。
|
|
 |
|
大波に洗われる堤防
|

|