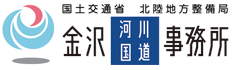- 金沢河川国道事務所TOP
- 治水
- 河川水辺の国勢調査
- 調査方法
河川水辺の国勢調査 調査方法
【魚類】【底生動物】【植物】【鳥類】【両生類・爬虫類・哺乳類】【陸上昆虫類等】
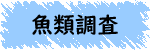
流量や、遡上時期、禁漁間などに応じて魚類相が十分に把握できる時期の夏季と秋季に2回調査しています。
調査方法は、投網(※1)、流し網(※2)、タモ網(※3)、角網(※3)、定置網、はえなわ、どう、セルビン、
網かご、潜水観察(※4)を実施します。
※1・投網:円形の網を水面に向かって投げ、魚類を網で覆い捕獲します。

※2・流し網: 帯状の網の魚群の進行を遮るようにあらかじめ設置したり、投げ広げたりした後、
網に追い込んで捕獲します。

※3・タモ網・角網:抽水植物や礫の間等に潜んでいる魚に対し、構えた網内に追い込んだり、
目視確認の後すくって捕獲します。


※4・潜水観察

このページの上へ|トップページへ戻る
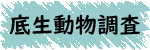
夏季と秋季2回実施しています。
調査方法は、定量採集(※1)(エクマンバージ型採泥器、チリトリ型金網)、定性採集(※2)(タモ網)を実施
します。
※1・定量採集:チリトリ型金網を川底に置き、付属のコドラートに入る石をめくり流下する個体を
金網で受け取ったり、石に付着した個体をピンセット等で採集します。また、水深の深い場所
では、エクマンバージ型採泥器を用いて底泥をすくい取り、泥内の個体を採集します。


エクマンバージ型採泥器 チリトリ型金網
※2・定性採集:タモ網を用いて、様々な環境に生息する個体について採集します。

このページの上へ|トップページへ戻る

春季と秋季2回実施しています。
調査は、調査地区内を歩きながら、生育する種を目視により確認し記録します。

目視による植物相調査
このページの上へ|トップページへ戻る
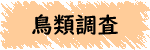
春季(春の渡り時期)、夏季(夏鳥の繁殖時期)、秋季(秋の渡り時期)、冬季(冬鳥の越冬期)の4回実施しています
(平成28年度)。
調査方法は、スポットセンサス法(※1)、集団分布地調査(※2)を実施します。
※1・スポットセンサス法:鳥類相を把握することを目的に1km毎に設定した調査箇所(スポット)で、
10分間の観察を行い、種及び個体数を記録します。

双眼鏡やスポッティングスコープによる観察
※2 集団分布地調査:鳥類の集団分布地を目的に、目視観察により「集団繁殖地」「集団ねぐら」
「集団越冬地」「集団中継地」「集団採餌地」「集団休息地」を調査し、集団分布地の位置と
状況を記録します。

カモメ類の集団越冬場所
このページの上へ|トップページへ戻る
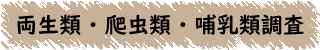
両生類・爬虫類は春から秋にかけて3回、捕獲および目視により調査します。哺乳類では目視によるほか、フィールド
サイン法(※1)により四季それぞれ1回、トラップ法(※2)では、春から秋にかけて調査します。
※1・フィールドサイン:水際・草むら等を調査し、足跡、糞などの痕跡を調べます。

フィールドサイン:キツネの足跡
※2・トラップ法:トラップ(罠)により捕獲します。


シャーマン型トラップ モールトラップ
このページの上へ|トップページへ戻る

陸上昆虫類を主体に、クモ類などを含めて生息状況を調査しています。調査は春、夏および秋の年3回以上、環境の
異なる種々の調査地区で陸上昆虫類等を採集し、その種類と出現状況を調べます。採集方法はスウィーピング法(※1)、
ビーティング法(※2)、ベイトトラップ法(※3)、ライトトラップ法(※4)などを用いています。
※1・スウィーピング法:おもに樹林地や低木林、草原で捕虫ネットを用いて、草や木の枝をなぎ
はらうようにしてすくい取ることで、採集します。

※2・ビーティング法:木の枝、草などを棒で叩いて、下に落ちた昆虫をネット等で受け取って採集
します。

※3・ベイトトラップ法:紙コップ・缶などを土に埋め、地上を歩き回る昆虫を採集します。

※4・ライトトラップ法:夜間に灯火に集まる習性を利用します。約1.5m四方のスクリーンを
見通しの良い場所に張り、その前に紫外線灯、昼光色蛍光灯、水銀灯をつるして点灯し、
スクリーンめがけて集まる昆虫を採集します。

このページの上へ|トップページへ戻る
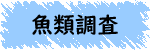
流量や、遡上時期、禁漁間などに応じて魚類相が十分に把握できる時期の夏季と秋季に2回調査しています。
調査方法は、投網(※1)、流し網(※2)、タモ網(※3)、角網(※3)、定置網、はえなわ、どう、セルビン、
網かご、潜水観察(※4)を実施します。
※1・投網:円形の網を水面に向かって投げ、魚類を網で覆い捕獲します。

※2・流し網: 帯状の網の魚群の進行を遮るようにあらかじめ設置したり、投げ広げたりした後、
網に追い込んで捕獲します。

※3・タモ網・角網:抽水植物や礫の間等に潜んでいる魚に対し、構えた網内に追い込んだり、
目視確認の後すくって捕獲します。


※4・潜水観察

このページの上へ|トップページへ戻る
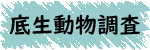
夏季と秋季2回実施しています。
調査方法は、定量採集(※1)(エクマンバージ型採泥器、チリトリ型金網)、定性採集(※2)(タモ網)を実施
します。
※1・定量採集:チリトリ型金網を川底に置き、付属のコドラートに入る石をめくり流下する個体を
金網で受け取ったり、石に付着した個体をピンセット等で採集します。また、水深の深い場所
では、エクマンバージ型採泥器を用いて底泥をすくい取り、泥内の個体を採集します。


エクマンバージ型採泥器 チリトリ型金網
※2・定性採集:タモ網を用いて、様々な環境に生息する個体について採集します。

このページの上へ|トップページへ戻る

春季と秋季2回実施しています。
調査は、調査地区内を歩きながら、生育する種を目視により確認し記録します。

目視による植物相調査
このページの上へ|トップページへ戻る
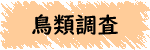
春季(春の渡り時期)、夏季(夏鳥の繁殖時期)、秋季(秋の渡り時期)、冬季(冬鳥の越冬期)の4回実施しています
(平成28年度)。
調査方法は、スポットセンサス法(※1)、集団分布地調査(※2)を実施します。
※1・スポットセンサス法:鳥類相を把握することを目的に1km毎に設定した調査箇所(スポット)で、
10分間の観察を行い、種及び個体数を記録します。

双眼鏡やスポッティングスコープによる観察
※2 集団分布地調査:鳥類の集団分布地を目的に、目視観察により「集団繁殖地」「集団ねぐら」
「集団越冬地」「集団中継地」「集団採餌地」「集団休息地」を調査し、集団分布地の位置と
状況を記録します。

カモメ類の集団越冬場所
このページの上へ|トップページへ戻る
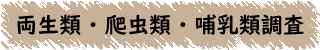
両生類・爬虫類は春から秋にかけて3回、捕獲および目視により調査します。哺乳類では目視によるほか、フィールド
サイン法(※1)により四季それぞれ1回、トラップ法(※2)では、春から秋にかけて調査します。
※1・フィールドサイン:水際・草むら等を調査し、足跡、糞などの痕跡を調べます。

フィールドサイン:キツネの足跡
※2・トラップ法:トラップ(罠)により捕獲します。


シャーマン型トラップ モールトラップ
このページの上へ|トップページへ戻る

陸上昆虫類を主体に、クモ類などを含めて生息状況を調査しています。調査は春、夏および秋の年3回以上、環境の
異なる種々の調査地区で陸上昆虫類等を採集し、その種類と出現状況を調べます。採集方法はスウィーピング法(※1)、
ビーティング法(※2)、ベイトトラップ法(※3)、ライトトラップ法(※4)などを用いています。
※1・スウィーピング法:おもに樹林地や低木林、草原で捕虫ネットを用いて、草や木の枝をなぎ
はらうようにしてすくい取ることで、採集します。

※2・ビーティング法:木の枝、草などを棒で叩いて、下に落ちた昆虫をネット等で受け取って採集
します。

※3・ベイトトラップ法:紙コップ・缶などを土に埋め、地上を歩き回る昆虫を採集します。

※4・ライトトラップ法:夜間に灯火に集まる習性を利用します。約1.5m四方のスクリーンを
見通しの良い場所に張り、その前に紫外線灯、昼光色蛍光灯、水銀灯をつるして点灯し、
スクリーンめがけて集まる昆虫を採集します。

このページの上へ|トップページへ戻る