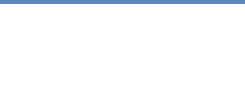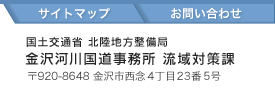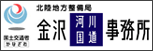第2回活動--令和6年5月24日(金)
令和6年度2回目の活動は、白山砂防事業概要、土砂災害の形態と災害事例、砂防設備の役割等について学びました。
手取川流域の主な災害事例を学び、土石流・がけ崩れの発生時映像等から土砂災害の危険性を改めて感じるとともに、砂防設備の効果事例についても学ぶことができ、砂防事業の必要性について理解を深める活動となりました。
併せて、今年度の広報活動に向けて、小学生向け見学案内の練習も行いました。
★参加人数★
7名
★学習内容★
1.白山砂防事業概要について
1)手取川流域の主な災害について
・昭和9年大災害
・平成11年甚之助谷土石流
・平成16年別当谷土石流
2)白山砂防事業・地すべり対策事業の概要について
・白山砂防事業の経緯
・白山地すべり対策事業の経緯
2.小学生向け見学案内の練習について
・館内施設の説明
・土砂流模型実験装置の演習
3.今後の活動について
手取川流域の主な災害事例を学び、土石流・がけ崩れの発生時映像等から土砂災害の危険性を改めて感じるとともに、砂防設備の効果事例についても学ぶことができ、砂防事業の必要性について理解を深める活動となりました。
併せて、今年度の広報活動に向けて、小学生向け見学案内の練習も行いました。
★参加人数★
7名
★学習内容★
1.白山砂防事業概要について
1)手取川流域の主な災害について
・昭和9年大災害
・平成11年甚之助谷土石流
・平成16年別当谷土石流
2)白山砂防事業・地すべり対策事業の概要について
・白山砂防事業の経緯
・白山地すべり対策事業の経緯
2.小学生向け見学案内の練習について
・館内施設の説明
・土砂流模型実験装置の演習
3.今後の活動について
- 第2回活動状況