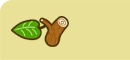
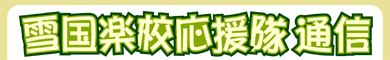

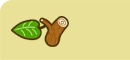 |
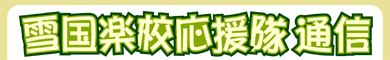 |
 |
| 平成15年7月16日発行 国土交通省湯沢砂防事務所 | ||
|
|
| 六日町小学校4年生(6月20日) |
|
||||||||
| <水生生物の調査グループ> | ||||||||
|
||||||||
| (子供たちの質問) ・ 魚野川の水生生物で絶滅したものはある? −見つからなくてもそれだけで「絶滅」とは決められない |
||||||||
| <水の汚れ、石・土・植物グループ> | ||||||||
|
||||||||
| (子供たちの質問) ・ 魚野川は昔よりも汚くなったの? −昭和30年頃には坂戸橋のあたりにもきれいな水にしかすまない ヤマメがいた。 ・ 油は川に流れているの? −微生物が分解してくれるのであまり流れていない。 ・ 川原を少しほったら赤い土の出てくるところがあるのはなぜ?昔からあったの? −山でよく見られる赤土と違ってここの赤土は鉄バクテリアという微生物が土の中の鉄を赤い色にしている。 ・ なぜぬるぬるしている石があるの? −ぬるぬるはケイ藻という生物。アユもケイ藻を食べる |
||||||||
 |