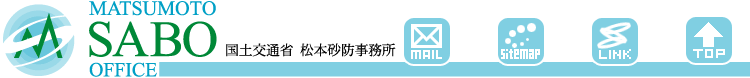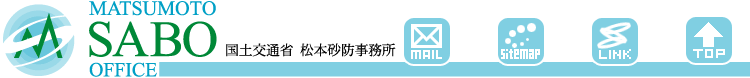塩の道 |
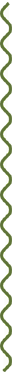 |
かつての糸魚川から松本まで30里、約120kmにわたって、日本海でつくられた塩を運ぶ街道がありました。千国に番所が置かれていたために千国街道と呼ばれた「塩のみち」です。塩は松本藩の塩留番所のあった塩尻まで運ばれました。この街道は、牛や馬の背に生活物資を乗せて往来する牛方や馬子、編み笠に背負子の歩荷(ポッカ)が大半だったといいます。運ばれる物資のなかでも山国にとって貴重だったのが塩でした。かつての街道沿いには、道中の安全を祈願した馬頭観音がいまも残ります。
街道の面影を残したハイキングのコースもあり、大町市では、旅姿の歩荷(ポッカ)や旅芸人の衣装の人達と一緒に歩く「塩の道まつり」も行われています。
|
|
 |
白馬大雪渓
幅100m、長さ3500m、標高差600mという日本一のスケールを誇る大雪渓で、シラネアオイ、キヌガサソウなどが見られます。雪渓登山は本格的な装備が必要ですが、雪渓の入口までならスニーカーで大丈夫です。
|
 |
高瀬渓谷
紅葉の景勝地として有名です。槍ヶ岳を源流とする水俣川が合流する高瀬川は、上流から高瀬ダム、七倉ダム、大町ダムと三つのダムが続いており、七倉ダムの下流には葛温泉の宿が点在し、野猿の遊ぶ姿も見られます。
|
|
 ヒスイ峡 ヒスイ峡
古くからヒスイの故郷として知られ、ヒスイ峡(硬玉産地)は国の天然記念物に指定されています。その歴史は縄文時代にまでさかのぼり、三種の神器の一つ「ヒスイの勾玉」の生産地、ヒスイ文化の発祥地として知られます。
|
 |
栂池自然公園
乗鞍岳の山腹に広がる日本有数の高山湿原群で、白馬三山、白馬大池などをはじめとして高山植物、湿原植物が四季を通じて楽しめます。
|
|