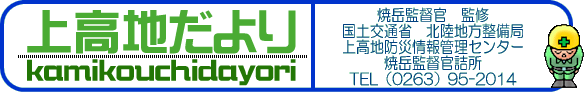
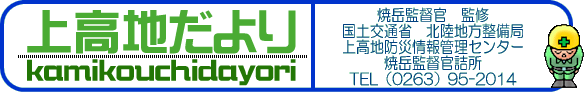
![]()
19.3.27 いよいよ仕上げの段階です。
![]()
福寿草の開花や、熊の出没など、春の便りが届き始めたかと思っていたら、
3月に入って、季節が逆戻りして
本格的な冬が来たみたいで、
日本海側からは大雪のニュースが伝えられました。
日本海側で雪の日は松本市(旧松本市)はだいたい晴れですが、
松本市安曇上高地はだいたい雪です。
とくに、日本海側で大雪になった3月12~13日にかけては、
南極のペンギンのように
みんなで風下を向いてひたすら耐えるしかないような
猛吹雪になりました。
さすがにこの吹雪の中、
人間が外に出て作業するのは危険……というより不可能なので、
運転席から建設機械を操作することでできる作業以外は中止しました。
上高地の冬の現場には、
「今冬は暖かく、天候に左右されず順調に工事が進む……」
などという甘い話は、やっぱり無かったようです。
厳しい条件下での施工でしたが、
現場の方々の地道な努力で事故もなく着々と進んできました。
梓川本川帯工工事は、きたる3月30日に「完成検査」を予定しています。
「完成検査」というのは、「工事が設計図書の通りにできているか。」
という検査です。
これに合格して初めて完成と認められて、
工事を請け負った業者さんに工事代金が支払われます。
完成検査に向けて、工事はいよいよ仕上げの段階に入っています。
写真は、2月22日(木)の第11号帯工です。

表面には現地で採取した自然石を張ってあります。
奥に見えるコンクリートの壁は護岸工です。
写真のままでも護岸として機能しますが、
こちらも景観に配慮して表面は布団かごで覆います。
下の写真は約1ヶ月後の、今日の写真です。

川底は以前と同じように整えられていて、
帯工はどこにあるかわかりません。
写真の真ん中付近に見える赤白のポールのところが第11号帯工です。
左奥のユンボ(パワーショベル)がいるあたりが第12号帯工です。
護岸工も、表面は現地で採取した石を用いた布団かごで覆われ、
こうして写真で見ると違和感はありません。
このあたりは、明神橋のすぐ下流で、梓川が左に急カーブするところです。
私たちが車でカーブする場合は、十分減速し、ハンドルを切って曲がります。
しかし、川の水は全速力で流れ下ってきて、岸に激突して跳ね返ることでカーブします。
その衝撃や複雑に渦巻いた水流が岸や川底を削るので、
大雨の時には被害を受けやすくなります。
昨年の「平成18年7月豪雨」で、この箇所の護岸が被災しました。
自然のままで、護岸がなかったら、
遊歩道が削られてなくなってしまうか、
さらにそこから水があふれて穂高神社や周りの施設が
水浸しになるかあるいは押し流されていたかもしれません。
もしそうなっていたら、観光客の皆様も怖い思いをしていたと思います。
開山後、上高地を訪れる皆様には、
以前と変わらぬ姿で、より安全になった上高地をご覧いただけることと思います。

![]()
19.2.28 この時期に上高地を訪れる皆様の、ご理解とご協力をお願いします。
![]()
桜が咲き始めたとか、熊が出たとか、福寿草が咲いたとか……あちこちから春の便りが届き始めています。
今年は、異常な暖かさですが、雪が少ないこともあって、工事は順調に進んでいます。
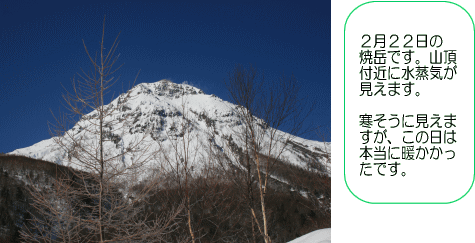
しかし、例年より暖かくて、雪が少ないとはいえ、そこは上高地。
「トンネルを抜けるとそこは雪国だった……」という有名な小説がありますが、
釜トンネルを抜けるとそこは「雪国」です。
そのため、今日、梓川本川帯工工事の現場に向かう途中の坂道で、
関西方面から工事用の資材を運んできたトラックが、坂を登れず立ち往生していました。
たくさんの工事用車両が通る道なので、大渋滞です。
工事車両が通る道は凍っています。
それが日中の暖かさで溶けるので、よけいに滑りやすくなるようです。
「乾いた氷は滑らない」というタイヤのCMがありましたが、その反対の状態です。
群馬県→新潟県は、谷川岳をくぐるので反対側が別世界なのも想像できます。
しかし、たかだか千数百㍍の釜トンネルの向こう側が別世界だなんて、
知らない人には信じられないことでしょう。
立ち往生していたトラックの運転手さんも、釜トンネルを抜けるまでは、
こんなことになるなんて、想像もしてなかったかもしれません。
冬場の工事には、こんなアクシデントもあるのです。
また、この坂道よりもう少し現場の方に行ったところに、
山肌から氷の塊が転がり落ちてくるところがあります。垂直に切り立った山肌に、
氷の壁ができていて、そこから氷の塊が落ちてくるのです。
この日の帰り道、直径30~50㌢くらいの氷の塊が、二つ落ちていました。
車を直撃されたらと思うと、ぞっとします。
工事関係者の方々は、十分注意して通行していますので、
これまでのところこの氷による事故は起きていませんが、
梓川本川帯工工事の恐怖スポットです。
そんな中で、梓川本川帯工工事は、現場の方々の地道な努力で、
事故もなく着々と進んでいます。
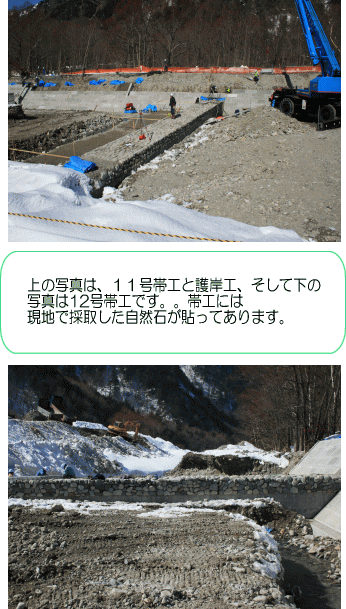
この日は、護岸工のブロックを積む作業を行っていました。
ブロック自体は重たいのでクレーンやユンボ(パワーショベル)で吊り上げますが、
そのブロックを隙間なく積み上げていくのは職人さんの手作業です。
この作業は、ブロック自体が重いので万一落下すれば大変なことになりますし、
厳冬期だと寒さで手の感覚が麻痺するので、危険を伴う作業です。
なお、護岸工は、このままでも護岸工として機能しますが、
周囲の景観と調和するよう、表面は現地で採取した自然石を使った布団カゴで覆います。

平成18年7月豪雨では、
昭和54年の台風11号の災害の時の約5割増しの雨が降りました。
しかし災害の規模は5割増しにはなりませんでした。
砂防施設は確実に効果を発揮しています。
この工事が終わった暁には、以前と変わらぬ姿で
さらに安全になった上高地にお目にかかれることと思います。
ところで、今年は暖かいので、この時期でも上高地を訪れる方が多いようです。
そこで、この時期に上高地を訪れる皆様にお願いです。
この時期、工事も追い込みに入っていますので、
たくさんの工事用車両が通過します。
工事用車両には十分気をつけるように徹底していますが、
皆様の方も、釜トンネルの中では歩道を歩く、などの
ご配慮とご協力をお願いします。
特に、釜トンネルは急な上り坂なので、
工事用車両も少々エンジンの回転をあげざるを得ません(別に乱暴な運転をしているわけではありません)。
そうするとどうしても排気ガスでトンネル内の視界が悪くなり、
歩行者に気づきにくくなります。
ですから、釜トンネル内では歩道を歩くなどのご配慮とご協力を賜りたいと存じます。
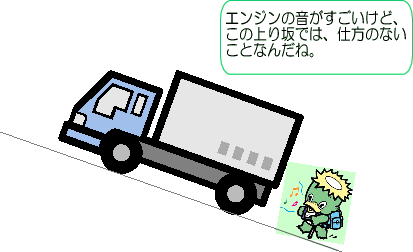
この日は、松本市奈川の魚伊羅津(うおいらづ)川の工事現場にも行きました。
なにやら難しい漢字を書きますが、
意味としては、多分、「魚居らず」なのだと思います。
魚も居ない荒れた川というのが由来だそうです。
かつてはそういう川だったのでしょうが、
今では釣りに訪れる人も多いようです。
この日は安全パトロールでした。
作業場所が狭い中で、整理整頓を行い、
安全に配慮しながら工事が行われていました。
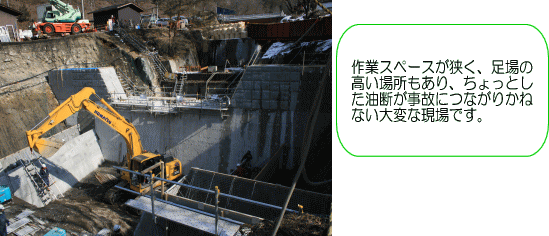
また、当事務所では「環境への配慮」というと、
上高地を代表として紹介するのですが、
上高地以外の工事でも
当然環境に配慮します。

こちらも、現場の方々の地道な努力で、事故などはなく着々と進んでいます。
工事完成の暁には、これまでと変わらぬ姿で、
魚も住める、より安全な魚伊羅津川にお目にかかることができるでしょう。
![]()