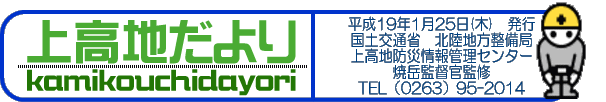 |
|
 |
上高地の明神橋下流では、現在、梓川本川帯工工事が行われています。
この時期に工事を行うのは「観光シーズンを」避けるためです。とはいえ、わざわざ気象条件のよくないこの時期に工事を行うのは、とても大変なことです。
この日(12月20日(水))の、工事現場付近の最低気温は朝の7時で−13.7℃。昼の2時には6度まで気温が上がりましたが、2時30分に陽がかげると、わずか10分足らずで1.5度まで気温が下がり、再び氷点下になりました。
|
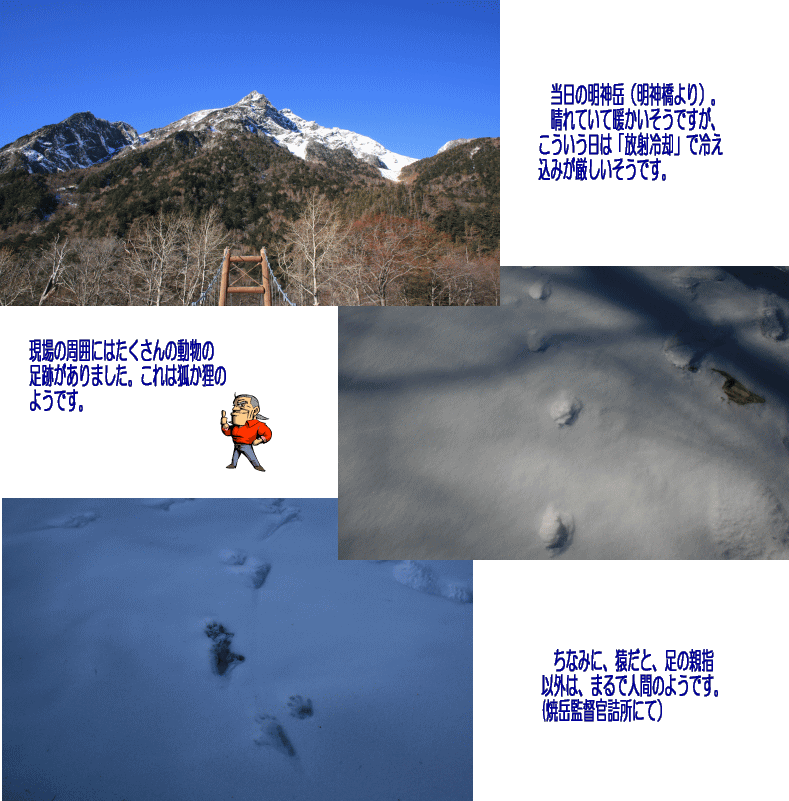 |
この日は安全パトロールの日でした。
建設現場での事故をなくすために、月に1回、発注者である松本砂防事務所の職員と、実際に工事を行う建設会社の社員の方々とで、工事現場を見て回り、安全対策がキチンとされているか、危険箇所には注意を呼びかける標示をしているか、などをチェックします。
梓川本川帯工工事は、この日、帯工を埋める場所を掘っている最中でした。
本格的な冷え込みに入ってしまうと、地面が凍ってしまい、ユンボ(パワーショベル)の歯が立たなくなるので、寒さが本格化する前に作業を進めたいのです。
氷でユンボの歯が立たないなんて!
現地の環境は、普段、暖房が効いた事務室で仕事をしているものからは想像もつかないほど過酷なようです。
|
 |
さて、実際に明神橋に行ったことがある方は、この写真を見て驚かれることと思います。
梓川の景観が一変してしまっています。
「何で、川をこんなふうにしちゃうの!?」
しかし、梓川を、こんなふうに変化のないまっすぐで平らな川にしてしまうわけではありません。
これは、川で工事を行う際に、下流の植生や水生昆虫や魚類を守るために必要なことなのです。
下の図のように帯工を施工しようとした場合、そのまま重機(ユンボとかブルドーザー)を川に入れて工事をすると、下流に泥水が流ます。
そうならないように、工事現場を仮の堤防で囲って、その中で工事をします。
|
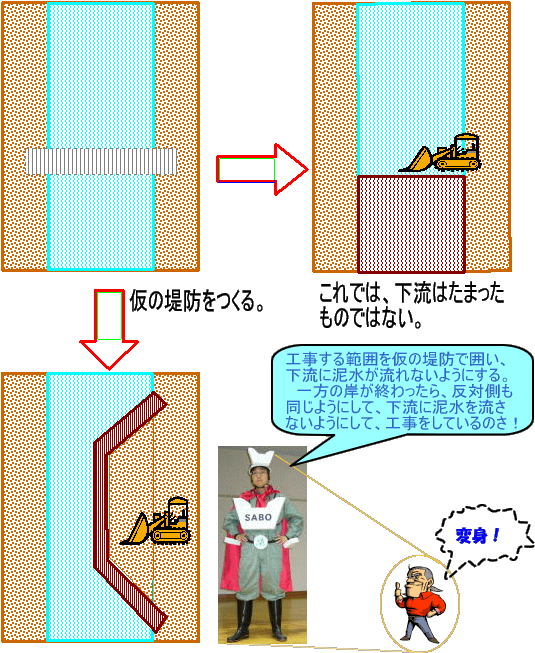 |
そのため、工事現場を見ると、川の風景が一変してしまうかのように思えますが、工事が終われば、元の川に戻ります。
ちなみに、同じように帯工設置工事を行っている松本市奈川の栃洞沢でも、同じように泥水をださないようにしています。

その工事現場のすぐ下流でイワナが釣れました。
魚たちに悪影響はないようでした。
釣りが許されるならば、梓川本川帯工工事の現場の下流でもイワナが釣れるものと思います。
1月の中旬までで、一番冷え込んだときで1月5日(金)の−17.8℃や、1月1日の−17.3℃など、−15〜16℃の範囲にとどまっていますが、これから本格的な冷え込みを迎え、−25℃という過酷な環境での工事になります。
現場で作業をする方々が健康で、無事故で工事を終え、より安全で美しい梓川になることを期待します。
|
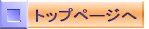 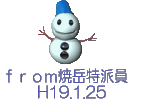 |