八右衛門沢という沢は、昭和54年でしたでしょうか、土石流を出しました。人の話によると、場合によっては帝国ホテルも危険ではないかと言われたような大きな土石流が起きたらしいです。
このときに、大正池周辺のカラマツ林が壊滅してしまいました。
カラマツというのはどういうところに林をつくるかと言いますと、焼岳のふもとに大きな扇状地があります。
大雨が降って水が流れ、いわゆる砂礫が動く場所は植物が育ちませんけれども、安定した期間が長いところへ育つのは、ほとんどカラマツとシラカンバです。このカラマツ、シラカンバという木は、よく日が当たって土が乾燥しているところによく育つわけですから、あの場所は林ができる最適地だろうと思います。
扇状地の川は普通、水が枯れていますが大雨が降ると一気に石と水が一緒に流れ出ます。それが砂礫の層となって堆積して行きます。
一方、通常水は上流で潜って、そして平らなところ、いわゆる扇状地の扇端と言いますが、そこへ来て湧き出します。これを泉と言っているわけです。そういう地形のところで、田代湿原というような湿原となります。
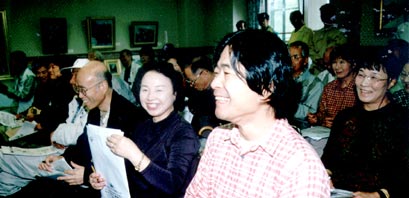
壊滅した林は、別の林に生まれ変わってきています。上高地では非常に多いケヤマハンノキ、あるいはタニガワハンノキというハンノキの仲間ですが、このハンノキとヤナギが川辺林の最初にできる林です。
そんなふうに昔の川原、川辺には氾濫が起こって、立派な林ができたのが全部流れてしまう。そしてまた新しい林が生まれてくるというようなことを繰り返していた場所が上高地の本当の姿だろうと思います。
今は堰堤がきちんとできて、氾濫ということはほとんど起こりません。そうすると林はどういうふうに変わってきたか。
林を見るとハルニレやサワグルミが非常に多いです。こういう林に変わってきています。さらに安定期間が長くなると、もちろんわれわれが生きている時代ではないですが、100年、200年のち、今、立派な川辺林は、場合によると針葉樹林に変わってしまうかもしれません。そんなふうな場所であるということです。