IT革命 in 黒部川
森さんが「IT」と言ったからかどうか判らないけどいつのまにか世の中IT(InfomationTechnology)一色である。
ITはオフィスから家庭までどんどん浸透している。
以前はアキバ系○タク人間(キムタク?)の専売特許だったE-mailやWorld Wide Webだが、今やi-modeさえあれば女子高生でも使いこなす様になってしまった。
さて、このITがらみで我が黒部川が何をやってるかというと最もがんばっているのが光ファイバによるインフラ整備。
来年の宇奈月ダム完成に合わせ、他の河川に先行して整備している。
一昨年くらいからあちこちの道路や堤防をほじくり返し、地域の皆さんにはご迷惑をかけていることと思います。m(_ _)m
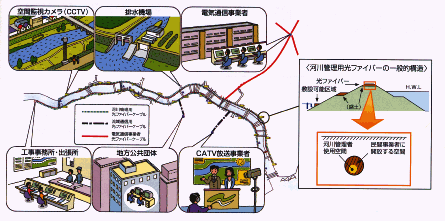
河川管理用 光ファイバー網
光ファイバは大容量高速で、地中埋設にすると災害にも強いことが先の阪神大震災でも認められた最強の通信インフラストラクチャーだ。
しかし、既存の電話線や無線などと違って敷設にものすごく手間がかかるのが欠点。
既存電話線を使ったDSLとかもそこそこ良いけど、あれは今んとこ首都圏限定だからねえ・・・
GHz帯の電波を使った伝送も大容量だけど地震によるアンテナのズレとか伝送の確実性など災害での利用を考えるとやはり光ファイバに勝るものはないだろう。
最近光ファイバで注目されているのは情報伝達の外にはセンサー利用。
光ファイバーで圧力や変位を検知と言うと「あたしには何のことやらさっぱりですぜ、御奉行様。」って感じですが、実際、光ファイバーは外力を受けるとその歪に比例して光パルスの反射光の周波数分布に歪がでるらしい。
その反射光の帰ってくる時間と波形のズレで歪の位置と歪(外力)の程度がわかるというしくみなのだ。(このしくみはブリルアン散乱光周波数シフトというらしい???)

ブリルアン散乱光

測定のしくみ
そう言えば攻殻機動隊(士郎正宗:講談社刊)ってSFマンガでサイボーグの感覚器官としてこれを使おうってのがあったなあ・・・
この計測センサーを護岸や堤防、ダムなどめちゃくちゃ延長が長くて、いちいち点検なんかしてられないぜ!っていうような構造物に入れておけば洪水による破壊やなにかが起きたときにすぐに異常の起きた場所や程度がわかるはず。
護岸や根固めの施工時に敷設ておけば土砂で埋め戻して見えない状態でも異変が分かるって言うのも利点だ。
図体がでかい河川構造物にも隅々まで神経が通うって感じだ。
このしくみはヨットのアメリカンカップの日本チームの船体に入っていて、「あ、この辺の歪が大きくなってるから修理しないと…」って言うように使われたらしい。
でもこのセンサーはセンサーとなる光ファイバーは安いんだけどブリルアン散乱光周波数シフトを検知する計測器が高いのが今のところ難点なのだ・・・
CCTV(リモートカメラをうちではこう呼んでる、何の略かは・・・忘れた(笑))画像も伝送に光ファイバーを利用しているが近年のエレクトロニクスの発達でこれも大きく様変わりしている。
CCTVはデジタル化と画像圧縮技術(MotionJPEG)で長距離送っても劣化しないで多量の画像を送ることが出来るようになった。
このような画像を使って画像解析で流速を測る、土石の移動を測るといった新技術も実用化している。
川のなかの流れを写して流れの中の模様やゴミなどを認識し、これらの動きを解析して水面上各部の流速ベクトルを抽出し、これらの合成ベクトルが流速として抽出できる。
また、画像解析技術を利用し、河岸の決壊やゴミの投棄などビデオ画像中で異変があったら知らせるというシステムも検討されている。
このへんは、防犯警備システムとかで利用されてるしね。
このように入力と通信のところは結構進んできてるが、問題は使い方と出力だ。
情報の整理・出力としてはGIS(Giographic Infomation System : 地図情報システム)などが使える。
これは電子地図にリレーショナルデータベースを組み合わせたシステムだが、リレーショナルだからどんなデータでも載っちゃう。
今のところ、河川の形状データや堤防、護岸の整備状況、構造物、生物の棲息状況などを載せる予定だがこれらの各項目はレイヤーというイメージでいくらでも追加できる。
だから、おいしいお店情報、イベント情報を載せて・・・とするとまるでカーナビか地図付きのタウン誌みたいだがまあ、あれも広い意味ではGISだといいえなくもない。
GISにこれまで述べた新技術で集めた情報を載せちゃうなども可能だ。
さらに、GISは情報配信や逆に情報の収集もweb上で出来るようになっている。
インターネットと接続すればうちからの配信だけじゃなくて市民の苦情とか河川敷の一時占用の申請とか、市町村の水防情報、地域情報など逆に情報をもらうことも可能だ。
こう見るとほとんど総合情報システムだなあ。
・・・とまあ、こんな感じで今やITは建設の分野でも注目されていて、まさに活き馬の目を抜くって状況だ。
いろいろなシステムが考案されて導入も進められている。
しかし、これらがどの様に使われるかやってみないとわかららない面もあると思う。
きっと開発したり整備した側も「あっ!」と驚くような使い方が出てくるんじゃないかな?
その例として、もともとはドコモさんがモバイルデータ通信用で整備したDoPaだけど、パケット料が高くてあまり利用されてなかったが今はi-modeで使われている。
DoPaが開発された頃でさえ既にデータ通信はマルチメディア化で画像やビデオ、音声といった大容量化が進んでいたが、この状況で文字中心で画像も94×72dotのGIFに制限されたi-modeがこれほど普及すると誰が予想しただろうか?
いま、盛んにITの整備、導入といっているが勝負は整備されてからじゃないかなあ?
今後も地域の安全とアメニティに役立つITの使い方を模索していくことになるだろう。
00/12/13
報告 : 調査課 Y