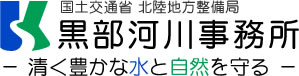黒部川でくろべ水の少年団が「水生生物調査」を行いました
水生生物調査は、多くの方々が河川に親しむ機会を提供し、河川愛護や水質浄化に関心を持っていただくことを目的に、昭和59年度から水生生物の生息状況を観察し、その生息状況から簡易的に水質状況を把握しています。
水生生物の調査方法は、川の中の水生生物を網等で採取したり、石に付着している水生生物を採取し、指標生物の写真や説明と見比べ、確認や分類を行った後、『きれいな水』『少しきたない水』『きたない水』『大変きたない水』の4段階で判定します。
黒部川では夏休み期間中に、黒部市内の小学4〜6年生から構成される「くろべ水の少年団(団員21名)」により、黒部川の上流部から下流部までの水生生物調査を実施しています。
今年の水生生物調査は、7月6日(日)に黒部川下流部を、8月23日(土)に黒部川上流部・中流部の計3箇所に調査地点を設けて実施しました。
7月6日の黒部川下流部は、黒部市飛騨地先の四十八ヶ瀬大橋下流左岸にて調査を実施しました。
調査は4班に分かれて、先ずは調査時の川の状況を把握する為、水温、流速、pH、COD(化学的酸素要求量)などを計測した後に水生生物の採取に取りかかります。
子供達は、川に生息する水生生物から水質を判定するために、沢山の水生生物を採取しようと元気いっぱいに川に入り、カワゲラやトビケラ等「きれいな水」の指標となる水生生物を採取しました。
8月23日の黒部川上流部は黒部市宇奈月町鐘釣地先にて調査を実施しました。
黒部峡谷鉄道により鐘釣まで移動し、河原におりると、周辺には河原温泉を楽しむ観光客が大勢訪れており、観光客を横目に調査を開始しました。
下流部と同様に川の状況を把握した後に水生生物調査の採取に取りかかりました。
上流部においても「きれいな水」の指標となる水生生物が採取されました。
次に中流部の調査を実施するため、黒部市音沢地先の音沢大橋上流右岸に移動しました。
中流部でも「きれいな水」の指標となる水生生物が採取され、また上流部の鐘釣地先よりも多種多様な水生生物が採取されました。
今回の水生生物調査の結果はまだ判定されていませんが、上流・中流・下流部共に「きれいな川」の指標となる水生生物が採取されました。
また、黒部川流域に住んでいる子供達と接する良い機会でしたので、河川水難事故防止の啓発や、触れる機会の少ない黒部川の砂防事業について、事務所職員より紹介しました。
くろべ水の少年団は、黒部川の歴史や環境等についても勉強しており、河川・海岸愛護の意識も高く、7月6日に実施された荒俣海岸清掃にも参加する等、河川・海岸美化の取り組みを実施しています。
※写真・「File Data」ボタンをクリックすると拡大写真・データを見ることができます。