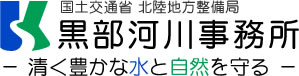「平成22年度黒部川水防工法研修会」を実施しました
6月5日(土)に黒部川左岸3.2km付近(四十八ヶ瀬大橋上流:国道8号バイパス)の黒部市沓掛地先の堤防において、黒部川水防工法研修会を実施しました。
「水防工法研修会」は、水防団が洪水時の迅速かつ的確な水防工法の実施を目的として訓練を行うものです。
水防工法とは、洪水時に河岸や堤防が洗掘や越水、漏水などによって崩壊するのを防ぐ様々な工法のことをいいます。本年の研修会では、縄結び・積み土のう工・木流し工・立籠工・川倉工・月の輪工・竹蛇篭の7工法の現地訓練を4人の講師を招いて実施しました。
※用語解説
1.河岸(かがん)・・・河川敷と水面が接する部分ののり面を河岸と言います。
2.洗掘(せんくつ)・・・のり面が流水の作用によって削り崩されることを言います。
3.越水(えっすい)・・・増水した河川の水が、堤防の高さを超えてあふれ出す状態のことを言います。
4.積み土のう工・・・洪水等で水が堤防を越えるのを防ぐため、土のうを積み上げる工法です。
5.木流し工・・・急流部において、流水を緩和して堤防崩壊の拡大を防ぐ工法です。
6.立籠工(たてかごこう)・・・堤防の法面に蛇籠を設置し、被災箇所を覆うことによって、洗掘を防ぐ工法です。
7.月輪工(つきのわこう)・・・堤防の裏側に漏水した水が噴き出している箇所で、土のうを積んで河川水位と漏水口との水位差を縮め水圧を弱め、漏水口が拡大するのを防ぐ工法です。
8.川倉工(かわくらこう)・・・流れを緩和して、堤脚洗掘の拡大を防止する工法です。
9.竹蛇篭工(たけじゃかごこう)・・・黒部川の伝統的な水防工法の一つで、竹で蛇篭を編み中に石を入れて、堤防や河岸の洗掘を防ぐ工法です。
当日は好天に恵まれ、黒部川水防連絡会関係者約100名が参加し、真剣な表情で各種工法に取り組んでいました。
参加者の中には、初めて水防工法を経験した人もおり、各水防工法の意義目的を周知することができ、有意義な研修会となりました。
これから梅雨期を迎えますが、いつ襲ってくるか分からない災害に向けて、このような工法で、被害をより少ないものにしていかなければならないことを改めて実感した研修会となりました。
※写真・「File Data」ボタンをクリックすると拡大写真・データを見ることができます。