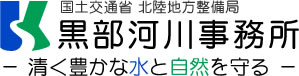三日市小学校児童が黒部川で「流れる水のはたらき」について学習しました!
11月10日(月)に、黒部市立三日市小学校5年生児童約60名と、担任の先生方と黒部河川事務所の職員とで、黒部川を見学に出かけました。
これは小学校の児童5年生が理科の授業の中で「流れる水のはたらき」について学習しているもので、小学校の先生から「実際に黒部川を訪れて学習してみたいと考えているが、ふだん黒部川を管理している黒部河川事務所の職員の方に水制や霞堤などの治水事業について現地で説明して欲しい」との依頼を受けて実施したものです。
当日は時折雨がぱらつき、肌寒い日でしたが、児童は小学校の先生や黒部河川事務所の職員の説明に耳を傾けながらメモを取ったり、活発な質問があったりと、水の流れについて一生懸命学習していました。
中でも、「水制」・「霞堤」といった説明では、身近な黒部川にこんな施設があるとは知らなかった様子で、感心している様子がうかがえました。
また、移動中にバスの中から工事をしている様子も見学し、普段はなかなか目にすることができない大きな作業用の機械も見学することができました。
ここで、黒部川の現地学習見学が終わった後、三日市小学校5年生の皆さんからお礼の感想文をいただきましたので、一部を紹介します。
・Aさん
私の心に残ったのは、堤防を三重にしていたことと、「水制」の話です。堤防を三重にしていたことでは、1つ目がこわれても、2つ目で戻す。2つ目が壊れても3つ目で戻す。この考えはすごいなぁと思います。これだと洪水も防げるし、安全だと思いました。「水制」の話は堤防を守ると言っていましたが、どうして間をあけておくのか不思議に思いました。この2つの方法を聞いて思ったのは「堤防」は大切ということです。
・Bさん
先日は黒部川について、とても詳しく資料までつくって下さり、ありがとうございました。特に印象に残っているのは、水制というブロックのことです。理由は、理科での考えが「ブロックを置く」という実験なので、実際にやっておられると知り、とても驚きました。
・Cさん
僕が一番驚いたことは、堤防が2、3重あったことと水制の大きさにとてもびっくりしました。その堤防が2、3重あったことで昭和44年の大洪水も一部のところでは被害を受けなかったことが一番心に残っています。黒部川の水を水力発電や農業用水に使っていると知って、黒部川は氾濫ばかり起こす川じゃなく、とてもいい川なんだなぁと思いました。
最近では、幼い子供たちが河川で遊ぶ光景が減ってきたように思います。幼年期に河川や自然等に触れることにより、自然を愛する心はもちろん、「正義感」の形成ができるといった調査結果も出ています。
黒部川を管理する私たち黒部河川事務所の職員も、気軽に足を運べるような環境整備をしていきたいと考えています。
三日市小学校の皆さん、お疲れ様でした。
※写真・「File Data」ボタンをクリックすると拡大写真・データを見ることができます。