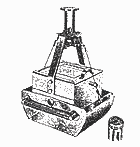![]()
|
1.底質の採集
「底質」とは、水底(海底、湖底等)の表面を構成している物質を指す言葉で、環境の視点からみると堆積物の性状やそこに含まれている成分の濃度を意味している。
底質を採集する器具を「採泥器」と呼んでおり、その作動原理により次の種類に大別される。
① ドレッジ採泥器 (dredges) :ひっかき方式
② グラブ採泥器(grab samplers):つかみとり方式
③ 柱状採泥器 ( core samplers ):打ち込み方式
|
|
2.各種採泥器の特徴
(1) ドレッジ採泥器
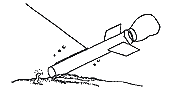 円筒形もしくは箱形の容器を海底面状で引きずることで底質を採集する方式で、歴史的にも最も古い。固い海底でも採泥できるように採集口に爪の付いたものや採集した底質を確保するために布袋が付いたものなどがある。 円筒形もしくは箱形の容器を海底面状で引きずることで底質を採集する方式で、歴史的にも最も古い。固い海底でも採泥できるように採集口に爪の付いたものや採集した底質を確保するために布袋が付いたものなどがある。
この方式では海底面を一定距離引き回すため、異なった底質の試料が混合されることや採取した位置が特定できないこと、さらには採取した泥の厚みがわからないことから、環境調査には通常用いられない。
|
|
(2) グラブ採泥器
左右に開いた試料採取部(バケット)を海底上で閉じることで底質をつかみ取る方式のもので、バネの力でバケットを閉じるものや海底に着くとバケットを開いていた金具がはずれ持ち上げる際自重で口が閉じるものなどがある。
この方式の特徴は、採集位置が特定できることと一定面積の範囲を採集できることで、環境調査では一番よく使われておりスミスマッキンタイヤ、エクマンバージ、港研式など種類も多い。
※今回実施した海域底質調査では、スミスマッキンタイヤ式の採泥器を使用しました。
|
|
|
(3) 柱状採泥器
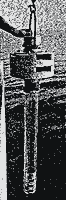 長尺の円筒形の採泥管を海底面に垂直に打ち込み、海底の堆積層を保持した状態で採集する方式で、自重で海底に突き刺さるものや採泥管がスライドするなどして海底に貫入してゆくものなどがある。 長尺の円筒形の採泥管を海底面に垂直に打ち込み、海底の堆積層を保持した状態で採集する方式で、自重で海底に突き刺さるものや採泥管がスライドするなどして海底に貫入してゆくものなどがある。
この方式は、海底面からの深さ毎の底質を比較する目的で使用される。採集された円柱形の底泥は海底面から一定間隔で切り分けられ、各試料毎に分析される。位置や採泥面積が特定できる点はグラブ採泥器と同じである。
|
|
【参考資料】
(1)「海洋調査フロンティア -海を計測する-」海洋調査技術学会(1993)
(2)「沿岸環境調査マニュアル〔底質・生物篇〕」日本海洋学会編(恒星社厚生閣:1986)
(3)「海洋環境調査法」日本海洋学会編集(恒星社厚生閣:1979)
|