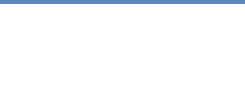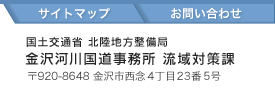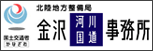第4回活動--令和6年7月24日(水)
令和6年度第4回活動は、牛首川流域にて白山砂防現場研修を実施し、砂防堰堤の改築工事現場や地すべり対策施設の施工現場等を見学しました。
普段は一般の方の立ち入りが禁止されているエリアの見学が多く、第11号排水トンネルの施工状況や第1号大口径集排水工の施工状況などについて各現場の監理技術者から直接お話をお伺いし、貴重な経験と濃い学びが得られた活動となりました。
★参加人数★
7名
★白山砂防施設メモ★
《百万貫の岩》
百万貫の岩は、昭和9年(1934年)7月に起きた「手取川大洪水」により誕生した。梅雨前線による記録的豪雨と残雪に伴う融水により、手取川と合流する宮谷川から、土石流によって約3km流れてきたと言われている。この付近には当時流されてきた巨石がたくさん点在している。
《猿壁砂防堰堤改築工事》
猿壁砂防堰堤は昭和38年に完成し、60年余りが経過していることから、著しい老朽化や損傷を受けている。このため、土石流や大規模土砂流出に備え、洗掘などの機能低下を抑え、嵩上げによる機能向上を図る。
土石流や大規模土砂流出などの災害に対する下流域の白峰集落や、迂回路のない生活・観光道路である県道白山公園線などへの安全度の向上を図る。
《第6号排水トンネル》
第6号排水トンネルは、左岸ブロックの地下水を排除するために、昭和62年から平成7年にかけて施工されている。
この排水トンネルは294.4mあり、甚ノ助谷の排水トンネル内でも最も長いトンネルとなっている。
近年では、地すべりの影響からトンネルが変状し、今後の施設の維持管理については考慮する必要がある。
《第1号大口径集排水工》
甚之助谷地すべりの問題を解決する大口径集排水工の特徴として、従来の重機や設備が不要となったことによるコストの削減や、排水効果の早期発現による安全率の上昇、動き続ける地すべりによる変形・せん断に強く、大口径による高い集水能力を有するという点がある。
《第11号排水トンネル》
甚之助谷地区の5つの地すべりブロックのうち、右岸上流ブロックの移動が明瞭に観測されたため、令和3年度より第11号排水トンネルの施工が進められている。
トンネル入口から約45mの地点にボーリング室を設置し、ボーリング室から集水ボーリングを扇状に配置することにより、地すべりの原因となる地下水の排除を図るものである。
《別当谷上流砂防堰堤》
別当谷上流域は土砂生産が激しく、平成16年5月には大規模な土石流によって、別当出合の登山用吊橋の流出等の被害が発生した。
度重なる土砂流出により、別当谷の既設砂防堰堤の損傷や老朽化が進行しているため、補修・補強等を行って機能保全を図っている。
現場は斜面からの落石が多く、施工の際は大きな危険が伴うことなどから、遠隔で工事車両を操作する無人化施工を推進している。
★猿壁砂防堰堤改築工事★
★第6号排水トンネル★
★索道撤去工事・第1号大口径集排水工★
★第11号排水トンネル★
★別当谷上流砂防堰堤★
普段は一般の方の立ち入りが禁止されているエリアの見学が多く、第11号排水トンネルの施工状況や第1号大口径集排水工の施工状況などについて各現場の監理技術者から直接お話をお伺いし、貴重な経験と濃い学びが得られた活動となりました。
★参加人数★
7名
★白山砂防施設メモ★
《百万貫の岩》
百万貫の岩は、昭和9年(1934年)7月に起きた「手取川大洪水」により誕生した。梅雨前線による記録的豪雨と残雪に伴う融水により、手取川と合流する宮谷川から、土石流によって約3km流れてきたと言われている。この付近には当時流されてきた巨石がたくさん点在している。
《猿壁砂防堰堤改築工事》
猿壁砂防堰堤は昭和38年に完成し、60年余りが経過していることから、著しい老朽化や損傷を受けている。このため、土石流や大規模土砂流出に備え、洗掘などの機能低下を抑え、嵩上げによる機能向上を図る。
土石流や大規模土砂流出などの災害に対する下流域の白峰集落や、迂回路のない生活・観光道路である県道白山公園線などへの安全度の向上を図る。
《第6号排水トンネル》
第6号排水トンネルは、左岸ブロックの地下水を排除するために、昭和62年から平成7年にかけて施工されている。
この排水トンネルは294.4mあり、甚ノ助谷の排水トンネル内でも最も長いトンネルとなっている。
近年では、地すべりの影響からトンネルが変状し、今後の施設の維持管理については考慮する必要がある。
《第1号大口径集排水工》
甚之助谷地すべりの問題を解決する大口径集排水工の特徴として、従来の重機や設備が不要となったことによるコストの削減や、排水効果の早期発現による安全率の上昇、動き続ける地すべりによる変形・せん断に強く、大口径による高い集水能力を有するという点がある。
《第11号排水トンネル》
甚之助谷地区の5つの地すべりブロックのうち、右岸上流ブロックの移動が明瞭に観測されたため、令和3年度より第11号排水トンネルの施工が進められている。
トンネル入口から約45mの地点にボーリング室を設置し、ボーリング室から集水ボーリングを扇状に配置することにより、地すべりの原因となる地下水の排除を図るものである。
《別当谷上流砂防堰堤》
別当谷上流域は土砂生産が激しく、平成16年5月には大規模な土石流によって、別当出合の登山用吊橋の流出等の被害が発生した。
度重なる土砂流出により、別当谷の既設砂防堰堤の損傷や老朽化が進行しているため、補修・補強等を行って機能保全を図っている。
現場は斜面からの落石が多く、施工の際は大きな危険が伴うことなどから、遠隔で工事車両を操作する無人化施工を推進している。
- 第4回活動状況
★猿壁砂防堰堤改築工事★
★第6号排水トンネル★
★索道撤去工事・第1号大口径集排水工★
★第11号排水トンネル★
★別当谷上流砂防堰堤★