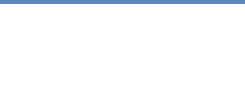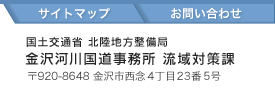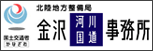第3回活動--令和6年6月3日(月)
第3回の活動は、早朝に起こった能登地方の地震(震度5強)により、午前の土砂災害防止広報キャラバン出発式と香林坊大和前のビラ配りは中止となりました。
午後からは、土砂災害防止広報キャラバンとして、白山市役所や鶴来支所・各市民サービスセンター(吉野谷、尾口、白峰、鳥越、河内)へ、特派員(キャラバン隊長)の2名が訪問しました。
キャラバン隊長以外の特派員は、手取川および海岸(美川工区・松任工区)の施工中または整備された現場を通じ、砂防・ダム・河川・海岸の治水事業の必要性を学びました。
★参加人数★
6名
★現場見学箇所メモ★
《手取川十八河原公園》 自然再生事業
昔の手取川は、広大な石の河原が広がっていたが、手取川ダムの完成や砂利採取などにより、一部区間で岩盤が露出していた。
手取川扇状地の特性を踏まえ、バランスのとれた河川環境の保全が図られるよう配慮しつつ、石川県の由来となった手取川の原風景である石の河原の復元に取り組んでいる。
《川北大橋付近》 急流河川対策
河川は水の流れによって自然に蛇行する形状をとり、侵食されやすい箇所が常時変化する。
侵食され、堤防が決壊することを防ぐため、弱部となる箇所については、盛土による補強(前腹付け盛土工)を実施している。
《西川・熊田川合流点処理》 樋門設置工事
西川と熊田川は、手取川と海岸砂丘に囲まれた低平地形に位置するため、手取川の水位が上昇すると自然排水が困難となり、合流点付近では過去に何度も内水による浸水被害が発生している。 また、合流部が閉じていないことから、計画規模の洪水が発生した場合には浸水被害が発生する恐れがある。
手取川からの外水氾濫を防止するため、西川と熊田川に樋門を設置する工事を実施している。
《美川工区》 人工リーフ
海岸堤防や消波工といった従来の工法で砂浜の回復等を図ってきたが、景観や砂浜へのアクセスのしやすさに配慮し、海岸堤防を緩傾斜堤に改築、消波工を人工リーフに転換することでよりよい海岸環境の創出を図っている。
《松任工区》 松任C.C.Z
昭和62年度に全国で先駆けて海辺のふれあいゾーン整備計画(C.C.Z整備計画※)の認定を受け、親しみやすい海辺づくりを目指した海岸保全施設の整備を行っている。
※C.C.Z:コースタル・コミュニティー・ゾーンの略。国土の整備・保全を図るとともに、人々が海と親しみ、集い憩える海浜地域を整備することを目的とした事業。
午後からは、土砂災害防止広報キャラバンとして、白山市役所や鶴来支所・各市民サービスセンター(吉野谷、尾口、白峰、鳥越、河内)へ、特派員(キャラバン隊長)の2名が訪問しました。
キャラバン隊長以外の特派員は、手取川および海岸(美川工区・松任工区)の施工中または整備された現場を通じ、砂防・ダム・河川・海岸の治水事業の必要性を学びました。
★参加人数★
6名
★現場見学箇所メモ★
《手取川十八河原公園》 自然再生事業
昔の手取川は、広大な石の河原が広がっていたが、手取川ダムの完成や砂利採取などにより、一部区間で岩盤が露出していた。
手取川扇状地の特性を踏まえ、バランスのとれた河川環境の保全が図られるよう配慮しつつ、石川県の由来となった手取川の原風景である石の河原の復元に取り組んでいる。
《川北大橋付近》 急流河川対策
河川は水の流れによって自然に蛇行する形状をとり、侵食されやすい箇所が常時変化する。
侵食され、堤防が決壊することを防ぐため、弱部となる箇所については、盛土による補強(前腹付け盛土工)を実施している。
《西川・熊田川合流点処理》 樋門設置工事
西川と熊田川は、手取川と海岸砂丘に囲まれた低平地形に位置するため、手取川の水位が上昇すると自然排水が困難となり、合流点付近では過去に何度も内水による浸水被害が発生している。 また、合流部が閉じていないことから、計画規模の洪水が発生した場合には浸水被害が発生する恐れがある。
手取川からの外水氾濫を防止するため、西川と熊田川に樋門を設置する工事を実施している。
《美川工区》 人工リーフ
海岸堤防や消波工といった従来の工法で砂浜の回復等を図ってきたが、景観や砂浜へのアクセスのしやすさに配慮し、海岸堤防を緩傾斜堤に改築、消波工を人工リーフに転換することでよりよい海岸環境の創出を図っている。
《松任工区》 松任C.C.Z
昭和62年度に全国で先駆けて海辺のふれあいゾーン整備計画(C.C.Z整備計画※)の認定を受け、親しみやすい海辺づくりを目指した海岸保全施設の整備を行っている。
※C.C.Z:コースタル・コミュニティー・ゾーンの略。国土の整備・保全を図るとともに、人々が海と親しみ、集い憩える海浜地域を整備することを目的とした事業。
- 土砂災害防止広報キャラバン
| 白山市役所(左)・鶴来支所(右)・市民サービスセンター訪問 | ||
- 現場見学
| 手取川十八河原公園について解説を受ける特派員 | ||
| 河川整備について解説を受ける特派員 | ||
| 美川工区(左)と松任工区(右)にて解説を受ける特派員 | ||