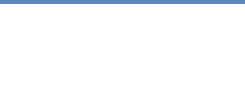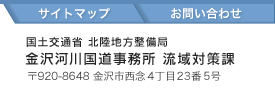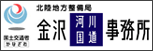白山砂防事業の歴史
大正元年 石川県により砂防工事に着手
明治43年、当時の石川県知事李家隆介が柳谷の荒廃状況を見て、このまま放置が許されないことを痛感し、翌44年より調査に着手。翌大正元年から手取川上流の甚之助谷・柳谷に山腹工や砂防堰堤を施工したのが、白山砂防の端緒である。
出水の度に被災し、県による工事は困難
大正3年,8年には集中豪雨のため、それまでの工事はほとんど全て破壊されたため、それまでとは抜本的に異なる対策として、谷を形成している表面の侵食防止と山脚の保護に重点を置く工事に切り替えた。
昭和2年より直轄砂防工事に着手
大正13年の砂防法改正により、「ソノ工事至難ナルトキ、又ハソノ工費至大ナルトキ」は国の直轄工事として行う道が開かれた。
石川県当局においては、早速大正15年(昭和元年)に内務大臣に請願書を提出し、翌昭和2年に国営の直轄事業とすることが認められた。
この年に、白峰村の別当出合付近に事務所(白山砂防工場)を新設した。初代所長は、日本の“砂防の父”と呼ばれる赤木正雄氏が着任した。
石川県当局においては、早速大正15年(昭和元年)に内務大臣に請願書を提出し、翌昭和2年に国営の直轄事業とすることが認められた。
この年に、白峰村の別当出合付近に事務所(白山砂防工場)を新設した。初代所長は、日本の“砂防の父”と呼ばれる赤木正雄氏が着任した。
昭和9年7月、未曾有の大水害発生
例年にない大雪で、残雪による融雪に梅雨前線豪雨が重なり、手取川流域の至るところで崩壊や土石流が発生し、沿川や下流扇状地に死者・行方不明者112名を数える未曾有の大災害をもたらした。しかし、砂防事業を行っていた柳谷・甚之助谷筋では崩壊が発生せず、砂防の効果が広く認識されることとなった。
昭和36年より直轄地すべり対策事業に着手
甚之助谷の基幹堰堤であった甚之助谷第5号砂防堰堤の移動(昭和2年〜35年までの移動量約10.5メートル)により、当地域が地すべり地であることが判明し、昭和30年より調査を開始した。
地すべり等防止法の施行後、一帯が地すべり防止区域に指定され、直轄地すべり対策事業が開始された。
地すべりの規模は日本最大級の地すべりであり、不安定土塊の総量は4千万立方メートルを超えると推定される。また、並行して砂防事業を実施しており、高度な対応が求められている。
地すべり等防止法の施行後、一帯が地すべり防止区域に指定され、直轄地すべり対策事業が開始された。
地すべりの規模は日本最大級の地すべりであり、不安定土塊の総量は4千万立方メートルを超えると推定される。また、並行して砂防事業を実施しており、高度な対応が求められている。
対策工事の様子
「河床に基岩の露出する箇所がないため、高堰堤の築造は困難とし、堤高8メートル内外のものをまず下流に建設し、これに土石の堆積するのを待って次年度に堆積土砂の上にまた8メートル内外の堰堤を設置する、所謂階段状の多数の堰堤によって両岸山地の崩壊を治める工法を我が国で初めて試みた。」(赤木正雄著:砂防一路より)。
平成16年度、甚之助谷砂防堰堤群は県内初の土木遺産に認定されました。