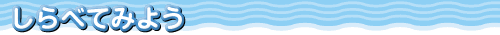 |
 |
| ほかにはどんな場所(ばしょ)で川の水が使(つか)われているかな? |
 |
| 川の水に関係(かんけい)したみんなのまちの特産物(とくさんぶつ)【農産物(のうさんぶつ)や工業製品(こうぎょうせいひん)など】を探(さが)してみよう。 |
 |
| みんなが飲(の)んでいる水道水(すいどうすい)はどこから運(はこ)ばれてきているのかな? |
 |
|
 |
|
| みんなの生活(せいかつ)を支(ささ)える大切(たいせつ)な川。ペットボトルを使(つか)って、川の水のきれいさを計(はか)ってみよう。 |
|
 |
| 1. |
下の穴(あな)を指(ゆび)でふさぎながら、川の水をいっぱいに入れます。 |
| 2. |
上からのぞきながら、標識板(ひょうしきばん)の4本の線(せん)がはっきりと見える深(ふか)さになるまで、下の穴(あな)から水をぬいていきます。 |
| 3. |
線(せん)がはっきり見えるところで指(ゆび)で穴(あな)をふさぎます。そのときの目もりの数字(すうじ)【透視度(とうしど)】が低いほど水がにごっていることになります。 |
|
 |
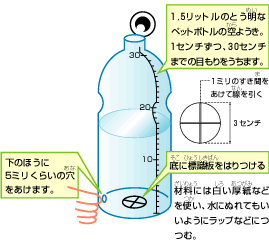 |
|
 |
・調べた場所
・水の色
・水のすきとおり具合(透視度(とうしど))
センチメートル |
|
 |
|
このページで紹介(しょうかい)したもののほかにもまだまだあるよ。
洪水(こうずい)にまつわる昔(むかし)の建物(たてもの)や石碑(せきひ)、千曲川(ちくまがわ)やその支流(しりゅう)に関係(かんけい)した文学碑(ぶんがくひ)などをさがして調(しら)べてみよう。 |
|
 |
洪水(こうずい)が多かった地域(ちいき)では、人々(ひとびと)が洪水(こうずい)とたたかったあとや洪水(こうずい)に備(そな)えてつくられた建物(たてもの)などを今(いま)でもたくさん発見(はっけん)することができるよ。
文学碑(ぶんがくひ)の中(なか)には、みんなも学校で習(なら)ってよく知っている歌が書かれているものもあるよ。? |
 |
 |
 |
洪水(こうずい)に備(そな)えて石積(いしづ)みをした民家(みんか)【更埴市(こうしょくし)】 |
 |
 |
 |
洪水(こうずい)のドロ水が流(なが)れこまないように工夫(くふう)された洪水除(こうずいよけ)の井戸(いど)【牛島集落(うしじましゅうらく)】 |
|
 |
〇見つけたもの
〇見つけた場所(ばしょ)
(左の地図の中にも印(しるし)をつけてみよう)
〇スケッチしてみよう
〇どんなことが書いてあるかな?
〇何のために建てられたものだろう? |
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
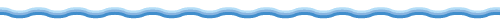 |
| Copyright
(c) 2003 THIKUMAGA Allrights reserved. |
 |