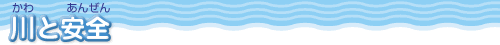 |
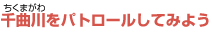 |
| 洪水(こうずい)などの災害(さいがい)を防(ふせ)ぎ、人々(ひとびと)の安全(あんぜん)なくらしを守(まも)るために、千曲川(ちくまがわ)とその支流(しりゅう)の川にはいろんな工夫(くふう)がされています。さまざまな施設(しせつ)がどんなはたらきをしているのか、実際(じっさい)にたしかめてみよう。 |
|
 |
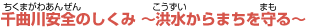 |
 |
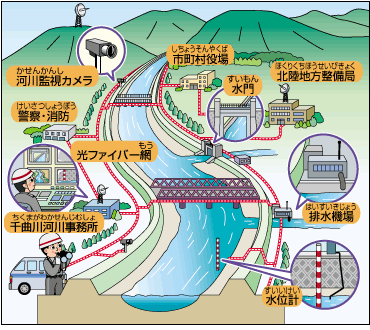 |
| 災害(さいがい)は起(お)きる前(まえ)に防(ふせ)ぐことがかんじん。 光ファイバー通信(つうしん)や河川監視(かせんかんし)カメラなどのハイテクを活用(かつよう)して、川のようすに異状(いじょう)が無(な)いか、いつも監視(かんし)の目を光らせています。 |
|
|
 |
 |
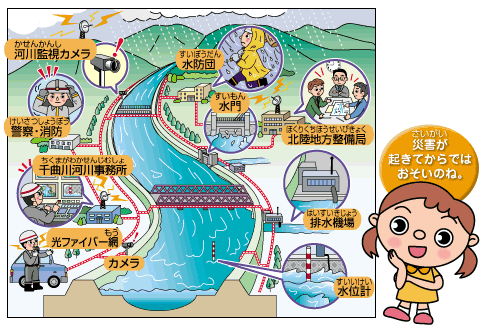 |
| 万が一、洪水(こうずい)が起(お)きそうな時にもすばやく対応(たいおう)。水門(すいもん)や排水(はいすい)ポンプの操作(そうさ)を行(おこな)ったり、また正確(せいかく)な情報(じょうほう)を水防団(すいぼうだん)の人に提供(ていきょう)し、洪水(こうずい)の被害(ひがい)を防(ふせ)ぐことが可能(かのう)になります。 |
|
 |
 |
 |
| 山崩(やまくず)れによる土砂(どしゃ)をためて、下流(かりゅう)へ流(なが)れないようにしています。 |
|
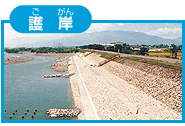 |
 |
 |
| 水の流(なが)れによって川岸(かわぎし)や堤防(ていぼう)がけずられるのを防(ふせ)ぎます。 |
 |
川(かわ)の水が逆流(ぎゃくりゅう)するのを防(ふせ)ぎます。 |
|
|
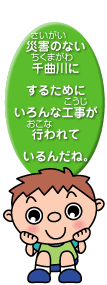 |
|
|
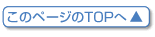 |
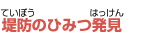 |
| 洪水(こうずい)を防(ふせ)ぐために、川岸(かわぎし)にそって土や石を高くもり上げたものが「堤防(ていぼう)」です。大きな川には「高水敷(こうすいじき)」とよばれる場所(ばしょ)が多く見られ、ふだん高水敷(こうすいじき)は公園(こうえん)やグランドなどいろいろな形で使(つか)われています。 |
|
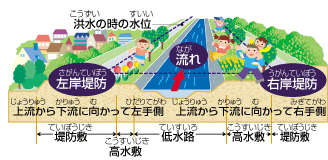 |
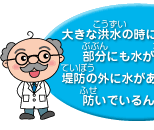 |
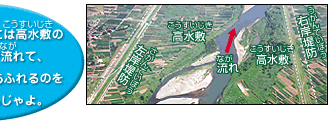 |
|
 |
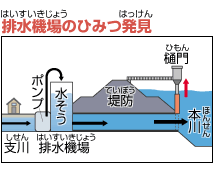 |
| 千曲川(ちくまがわ)が洪水(こうずい)になった時、支流(しりゅう)の川の水があふれ出さないようにポンプを動(うご)かして排水(はいすい)を行(おこな)うための施設(しせつ)です。 |
|
 |
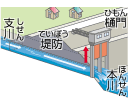 |
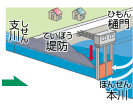 |
| 1.ふだん、支流(しりゅう)の川の水は自然(しぜん)に千曲川(ちくまがわ)に排水(はいすい)されます。 |
|
| 2.千曲川(ちくまがわ)の水かさが増(ふ)えたときに樋門(ひもん)を閉(と)じ、川の水が逆流(ぎゃくりゅう)してこないようにします。 |
|
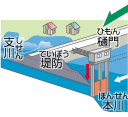 |
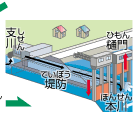 |
| 3.出口(でぐち)をふさがれた支流(しりゅう)の川の水の高(たか)さは上昇(じょうしょう)を続(つづ)けます。 |
|
| 4.支流(しりゅう)の水があふれないように排水機場(はいすいきじょう)によって千曲川(ちくまがわ)に水を逃(に)がします。 |
|
|
|
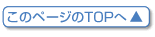 |
 |
 |
|
|
 |
| 洪水(こうずい)などのとき、水による災害発生(さいがいはっせい)をけいかいし、防(ふせ)ぎ、または被害(ひがい)を最小限(さいしょうげん)にとどめることを「水防(すいぼう)」といいます。千曲川流域(ちくまがわりゅういき)の安全(あんぜん)を守(まも)るために、地元(じもと)の消防団(しょうぼうだん)や水防団(すいぼうだん)を中心(ちゅうしん)に、消防(しょうぼう)や警察(けいさつ)、県(けん)や市町村(しちょうそん)など多くの人たちが水防活動(すいぼうかつどう)にがんばっています。 |
 |
 |
| 水防演習(すいぼうえんしゅう)の様子(ようす) |
|
|
 |
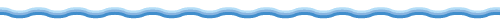 |
| Copyright
(c) 2003 THIKUMAGA Allrights reserved. |
 |