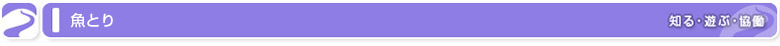
川の流れを石や草木でせき止め、中の小魚を素手や持ってきた網でとったり、ありあわせの手ぬぐいなどでも大丈夫。
|
| 本流や支流から中州の端へ流れを誘導し、留場をつくっておくと、そこに魚が集まってくることがあります。そこへ30センチくらいの「かっちん石」と呼ぶ石を投げ込んで、魚の気絶したところをすばやく拾いあげるのです。 |
|
|
|
小枠の底にガラスをはった手製の水鏡(箱目鏡ともいいます)で水の中をのぞきながら、大きな石のかげに潜んでいる魚を、ツキでつきさしてつかまえる方法です。ツキは竹の先へ三つまたの針(やす)をつけた簡単なものです。
このようにして魚をとることは今では、法律で禁じられています。 |
|
|
|
| うけの中には竹でつくった「どう」とガラスやプラスチックで作った「セルビン、ガラスうけ」の2種類があり、魚とり用の道具として、うけの中にえさを入れ、口を下流のほうに向けて仕掛けます。えさにつられた魚が中に入ると、出られない仕掛けになっています。川へ水浴びに来たときに仕掛けておくと、夕方の帰りがけまでには、1、2尾かかっていたり、1晩仕掛けるとかなり魚がとれました。でも今は竹で作ったうけ以外のプラスチックやガラスで出来たうけ(セルビン)は、法律で使用が 禁じられています。 |
|
|
|
| たこ糸に釣り針を何本もつけ、えさにドジョウなどをつけて流れに沈めて張ります。夕方川に流しておき、朝かかったウナギをあげます。 |
|
|
|
| エゴマの実の油をしぼったかすを「いかす」といいます。いかすを水面にまき、さおの先に何本もかえしのない釣り針を仕掛けた釣りざおで、集まってきた魚をすばやくひっかけ、うしろへ投げてとります。 |
|
|
|
| サワクルミの葉をたくさん取ってきて、カジカのいそうな流れをせき止め、その上流でクルミの葉を石でつぶしてアクを出して流します。20分もすると魚はクルミの葉のアクにあたって浮いてきます。このようにして魚をとることも今では法律で禁じられています。 |
|
|
|
| ウグイやオイカワの生まれたばかりの稚魚が群れている場所で、手ぬぐいを2人の子供が広げ、そっと魚を手ぬぐいですくいあげるのです。 |
|
|
|
| 竹や金網でできたざるを使い、ざるを水草の中や水際の草、ゴミの下にざるをはり、足で水草の中を追って、ざるの中に魚を追い込んで魚をとります。 |
|
|
|
| 水の中や水際にあるゴミや水草の中にかくれている魚をゴミや水草の中に手をそっと入れてつかみ取りします。 |
|
|
|