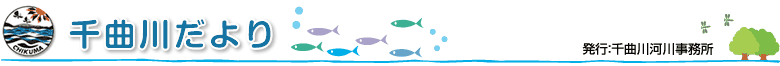掲載日 2010/06/18
特定外来生物「オオカワヂシャ」の駆除研修会が開催されました
オオカワヂシャはアレチウリに比べ、特定外来生物としての認識が低く、駆除の取り組みが少ないことなどから、6月15日に千曲市須坂の冠着(かむりき)橋左岸下流において、長野県環境部の主催としては今年度で3回目となる「オオカワヂシャ駆除研修会」が開催され、長野県、千曲市、長野市、須坂市などの職員はじめ、千曲川河川事務所及び戸倉出張所も含めて総勢約20人が参加しました。
 |
 |
研修会では作業に先立ち、環境省長野自然環境事務所と長野県環境保全研究所から生態などについて説明があり、これによるとオオカワヂシャは、湖沼や河川の岸辺など湿地に生育する植物で、長野県内では平成19年に千曲川で初めて生育が確認され、その後、犀川や奈良井川、天竜川などでも確認されており、その繁殖の拡大が懸念されています。
在来種で準絶滅危惧種のカワヂシャと比べると全体は一回り大きく、花はカワヂシャが小さな白色の花をつけるのに対し、オオカワヂシャは多数の淡紫色の花をつける点で見分けることができます。両種は同じような環境に生え交雑することが知られているため、在来種の生育が危ぶまれているとのことでした。
 |
 |
基礎知識を習得してから手作業による駆除作業に入りましたが、オオカワヂシャは水が溜まってよどんでいるような場所に生息するため作業するにも足場が悪く、引き抜くことは簡単ですが、茎が長いことや繁殖範囲が広いため、作業は困難をきわめましたが、今回の駆除作業で、軽トラック約1台分のオオカワヂシャを駆除しました。
今後もオオカワヂシャの認識を広めるとともに、関係機関や地元の方々のご協力を頂きながら、正常な河川環境の保全に努めてまいります。